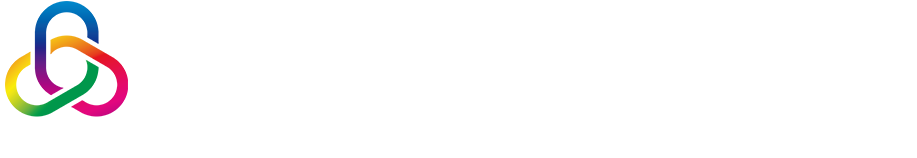センター長挨拶
京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センター長挨拶
2021年(令和3年)4月、京都大学大学院法学研究科による学際的・国際的な法政策研究の拠点として法政策共同研究センターが設立され、今年で5年目を迎えました。
本センターは、科学技術の進歩、急速なグローバル化や地球環境の変動などに伴って生じる社会システム全体のパラダイムシフトに対応するために、先端的な法政策課題について理論と実務が協働して学際的・国際的研究に取り組み、誰一人取り残さない、人間を主体とするイノベーションの実現を支える法政策構想を提案するとともに、新しい学術領域の開拓とその独創的な担い手の養成を目的としています。
本センターには、共同研究のための基本組織として、「人工知能と法」、「医療と法」、「環境と法」、「少子高齢化社会と法・政治」の4つのユニットが置かれています。また、「法文化国際研究」、「政策実務教育支援」の2つのセクションに加えて、2024年(令和6年)4月には、「文理融合実証研究」セクションを新たに設置して、従来の法学・政治学の伝統的な研究領域に収まらない先端的な研究や、人文科学や自然科学の諸分野との学際的研究を、法律・行政の実務家、学内他部局、学外あるいは外国の研究機関等と連携して実施しています。
各ユニットの活動には、以下のようなものがあります。人工知能と法ユニットでは、アジャイル・ガバナンスの考え方に基づき人工知能技術の社会実装に向けた法制度に関する国際的研究を進めており、2023年(令和5年)に開催されたG7広島サミットのデジタル・技術大臣会合の下のタクス・フォースにおいて“Governance Principles for a Society Based on Cyber-Physical Systems”の取りまとめを主導するなどの成果を挙げています。医療と法ユニットも、令和5年4月に発足した医学研究科附属医療DX教育研究センターと連携して、医療DXの実現に必要な医療情報法制に関する共同研究を実施するとともに、2024年(令和6年)4月に開設された医学研究科附属ヘルスセキュリティセンターとの共同研究に着手しています。さらに、2023年(令和5年)10月には、少子高齢化社会と法・政治ユニットを立ち上げ、各国で大きな課題となりつつある少子高齢化問題に関して国際的な共同研究を進めているほか、2024年(令和6年)4月に環境と法ユニットの専任教員が着任し、本格的に学際的な共同研究を始めています。
また、各セクションでは学際的・国際的な研究を進めるための方法開発や国外の研究機関との連携に重点を置いています。文理融合実証研究セクションは、データサイエンスや実験社会科学の手法を用いた学際的な共同研究を駆動し、法政策研究の実証的な基礎を提供することを目指すものであり、2024年(令和6年)4月に担当教員2名、さらに12月には担当教員1名が着任しました。法文化国際研究セクションでは、ウィーン大学、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所やチューリッヒ大学等との国際共同研究を推進しています。
このように、本センターは、科学技術の発展等が社会にもたらす先端的な法政策課題について、社会の各方面と協働して学際的・国際的研究を推進し, 国際ルール・国際標準の構築等に向けて先導的な役割を果たしていきますので、本センターの活動へのご協力、ご支援を宜しくお願いいたします。
待鳥聡史(京都大学大学院法学研究科教授、法政策共同研究センター長)
センター長紹介

待鳥聡史(京都大学法学系(大学院法学研究科)教授、比較政治・アメリカ政治)
1971年生まれ。1993年、京都大学法学部卒業。京都大学大学院法学研究科修士課程を経て、ウィスコンシン大学(アメリカ)で修士号、京都大学で博士号を取得。大阪大学助教授、リフォルニア大学サンディエゴ校客員研究員などを経て、2007年から京都大学大学院法学研究科教授。この間、2012〜15年および2020年〜24年は公共政策大学院に所属(大学院法学研究科・法学部兼担)、22〜24年には公共政策大学院長。
アメリカ学会清水博賞(2003年)、サントリー学芸賞(2012年)を受賞。Social Science Japan Journal国際編集委員。
比較政治論を専攻し、アメリカや日本の政治制度とその帰結に関する研究を行ってきた。
主な研究業績は、単著として、
『財政再建と民主主義』(有斐閣、2003年)、『首相政治の制度分析』(千倉書房、2012年)、『代議制民主主義』(中公新書、2015年)、『政治改革再考』(新潮選書、2020年)、Political Reform Reconsidered (Springer, 2023) など。
共著・共編として、
『日本の地方政治』(曽我謙悟と共著、名古屋大学出版会、2007年)、『比較政治制度論』(建林正彦・曽我謙悟と共著、有斐閣、2008年)、『「憲法改正」の比較政治学』(駒村圭吾との共編、弘文堂、2016年)、『〈やわらかい近代〉の日本』(宇野重規との共編、弘文堂、2024年)など。
論文として、
“The Last Two Decades in Japanese Politics: Lost Opportunities and Undesirable Outcomes” in Yoichi Funabashi and Barak Kushner (eds.), Examining Japan’s Lost Decades (Routledge, 2015); “Intellectual Origins of Post-1990 Political Reforms in Japan” in Kazuhiro Takii (ed.), The Lost Two Decades and the Transformation of Japanese Society (International Research Center for Japanese Studies, 2017) など。
副センター長紹介

佐々木健(京都大学法学系(大学院法学研究科)教授、ローマ法)
1978年生まれ。2001年京都大学法学部卒業。京都大学博士(法学)。京都大学大学院法学研究科助手、同准教授を経て、2018年より現職。この間、2009年~2011年まで、ローマ大学(ラ・サピエンツァ)にて在外研究。
法制史学会理事、ローマ法雑誌編集委員会事務局、Accademia Romanistica Costantiniana会員。
著書に『古代ローマ法における特示命令の研究』(日本評論社、2017年)、編著書に『ラテン語法格言辞典』(柴田光蔵、林信夫と共編、慈学社、2010年)、『身分と経済——法制史学会70周年記念若手論文集』(額定其労・髙田久実・丸本由美子と共編、慈学社、2019年)など。
論文としてWho could apply for the interdicts concerning «via publica»? – An analysis of Ulp. D. 43.8.2, in: Revista General de Derecho Romano, vol. 19 (2012); Roman-Japanese Legacy with the Appointment of second Degree Successor: An Analysis of the second Petty Bench’s Judgment (Japanese Supreme Court) on 18th March 1983, in: Ulrike Babusiaux, Mariko Igimi (eds.), “Messages from Antiquity”: Roman Law and Current Legal Debates (Böhlau, 2019)など。