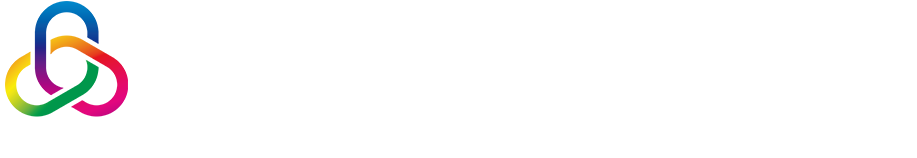出版助成
概要
本センターでは、本学の法学研究者による研究成果の公表・発信を促進するとともに、特に若手研究者のキャリア形成の一助となるべく、若手研究者を中心に出版助成を行っている。
2024年度の助成対象
木下岳人『子会社事業の被害者に対する親会社の不法行為責任』(商事法務、2025年)
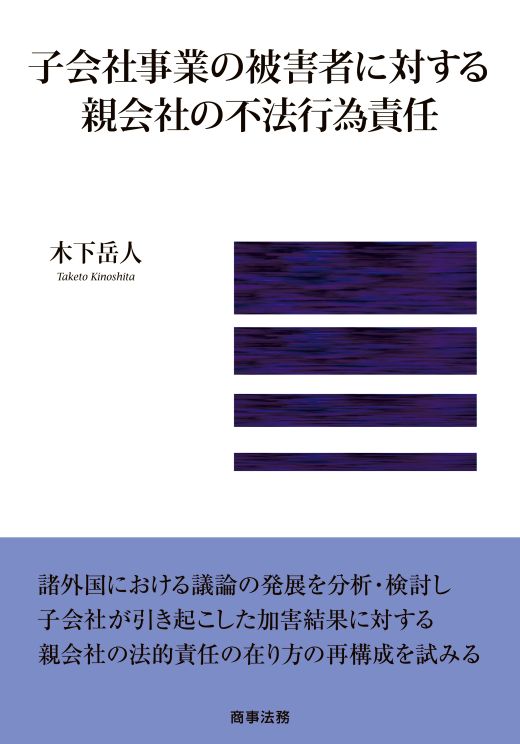
自著紹介
子どものころから本が大好きでした。また、大人になってからは法律が仕事になりました。なので、法律に関する自分の研究が活字となることはまさに夢のような出来事です。しかし、出版不況とも言われるこの時代、夢をかなえることは簡単ではありません。一般的に採算がとりにくいと言われる学術書ではなおさらです。しかし、法政策共同研究センター様のご支援と出版社様のご厚意のおかげで、このたび研究書を上梓することが叶いました。まずはこの場をお借りして、皆さまに心より御礼を申し上げます。
私の研究は、ざっくりいえばこれまで主に商法の世界で問題とされてきた課題に対して民法を使ったアプローチで解決できないか、というものです。日本をはじめ主要国の法制度では、株主有限責任や法人格の独立性を根拠に、子会社がどれだけ負債を抱えても親会社(株主)にはその責任が及ばないというのが原則です。そのため仮に子会社が第三者にどれだけ深刻な加害結果をもたらしても、その第三者(被害者)から親会社に対して責任追及をすることはできないというのが一般的な帰結になります。しかし、本当にそうなのでしょうか。
本書では留学先であったイギリスにおける近時の判例法理の発展に着想を得て、日本法下においてもそれと近似する法律構成の可能性を探りました。とはいえ、日本の裁判所で「外国ではこうなんです」と主張するだけでは認めてもらえません。あくまで日本の法律や判例・学説を土台にしつつ、それに外国法という補助線を引いてみることで、現実の紛争解決での活用に耐えうる責任判断のフレームワークの構築を試みています。それが成功しているかは読者の皆さまのご批判を待つ他ありませんが、近時の「ビジネスと人権」についての関心の高まりを背景として、イギリス以外の国でも同様の紛争事案が相次いで問題となっています。こうした世界的潮流に鑑みると、日本においても司法がこの問題に正面から向き合わなければならなくなる日が来るのは時間の問題と言えそうです。
法政策共同研究センターの将来構想では、「学際」「国際」「実務」の3つの視点の統合が挙げられています。本書をお読みになった方が、上記の理念に適う要素を少しでも感じとってくださったのであれば大変光栄に思います。
著者略歴
2012年早稲田大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了。2015年12月最高裁司法研修所修了、弁護士登録(第68期)。2020年University of Leeds(LL.M)修了、2023年University of Illinois Urbana Champaign客員研究員、2024年京都大学大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程修了(博士(法学))。
杉本拓海『親権の行使と可罰性』(成文堂、2025年)
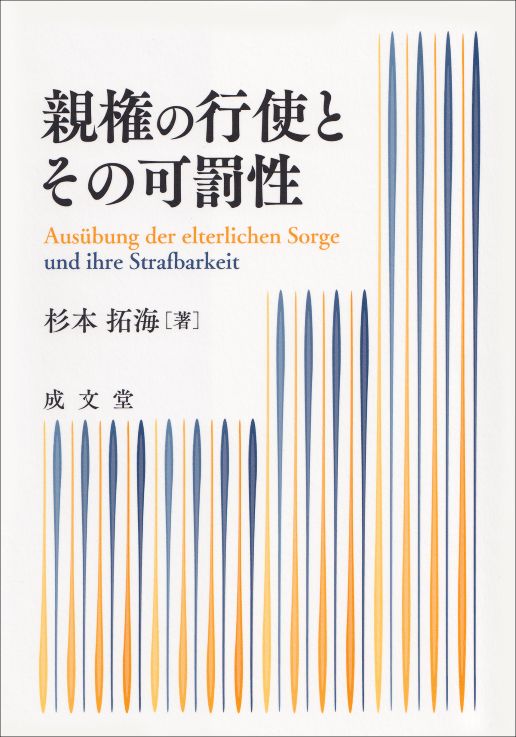
自著紹介
子育ての場における体罰という名の暴力は,かつては一定の範囲内であれば民法に定められた懲戒権の行使として認められ,刑法上も正当化されうるものと考えられていました。しかし,平成末期に「しつけ」を口実とする虐待事件が社会問題となり,法改正によって体罰が明文で禁止され,民法の懲戒権規定も削除されるに至りました。一方で,最近の裁判所は子に対する暴力に対して厳しく対処しており,処罰範囲の過度の拡大が懸念される事例もみられます。本書は,このような法制度の変遷と価値観の変化を踏まえ,親が子に対して行う行為の許容される範囲と刑法的に可罰的と判断される範囲の境界線について可能な限り言語化して明らかにしようとするものです。
本書では,まず,親が子に対して行う行為の正当化の根拠となる民法上の親権・懲戒権規定について整理し,議論のための土台を得ます。その上で,懲戒権規定の残る教師の懲戒権と民法上から削除された親の懲戒権の関係性を検討し,教師の懲戒権の行使が問題とされる裁判例を分析することで,その傾向を明らかにします。また,日本よりも早い2000年にはすでに体罰禁止が明文化されているドイツにおける議論を比較対象として分析します。そして,以上を踏まえて親の措置が許容される限界を示すことを試みます。
少子高齢化が進行し子育て支援の重要性が叫ばれる一方,核家族化,初産年齢の高齢化が進み,共働き世帯が増加する現代においては,育児に割くことができる人的・時間的リソースが限られています。さらに,現在の子育て世代は自らの幼少期とは異なる社会常識のもとで育児をする難しさにも直面しています。本研究は,親として許される行為の範囲とその理由を検討し,一定の指針を示すことを通じて,このような子育ての推進を課題とする社会に貢献することを目指す営みです。また,そのテーマから必然的に刑法という単一の法領域のみでなく,民法や行政法についても広く検討の対象とするものであり,親の行為の許容される限界を検討するにあたっては脳科学分野の文献も一部参照しています。このように,本研究は,パラダイムシフトに対応するために学際的・国際的な視点から先端的な法政策課題について取り組み,誰一人取り残さない法政策構想を実現するという法政策共同センターの理念と通底するものであると信じております。
今回,本センターの出版助成を賜り,厳しい出版情勢の中にもかかわらず本書を世に出す機会をいただきました。若手研究者としてまだ歩み始めたばかりではありますが,本書が今後の子育てに関する法政策の議論の一助となることを願っています。そして,本センターの支援により,本研究を公表する貴重な機会をいただけたことに深く感謝申し上げます。
著者略歴
1991年6月 大阪にて生まれる
2015年3月 京都大学法学部卒
2017年3月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了
2020年3月 京都大学大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程修了 博士(法学)
2020年4月〜
2023年3月 京都大学大学院法学研究科 特定助教
現職 大阪経済法科大学法学部 准教授
大村華子『日本の経済投票―なぜ日本で政権交代が起こらないのか?』(有斐閣、2025年)
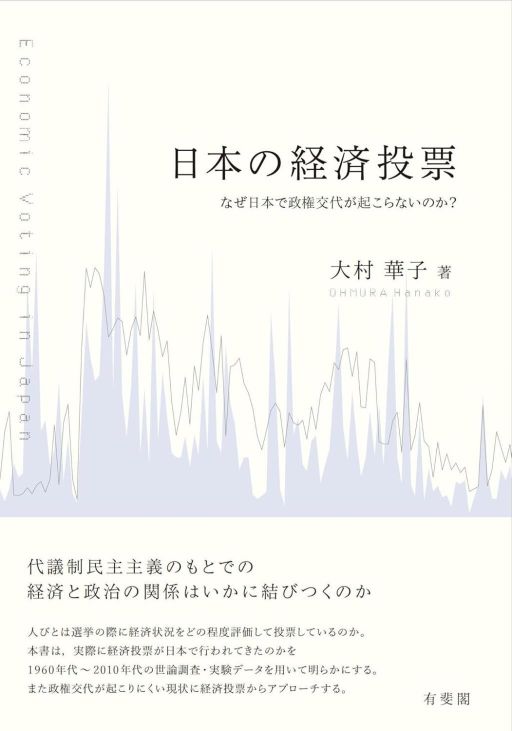
自著紹介
民主主義の政治体制と自由主義の経済体制のもとで、政治と経済が密接につながっていることは周知の事実です。では、有権者であり、消費者でもある私たちは、経済への評価を、どの程度政治的評価につなげることができているのでしょうか。この問いは、政治学、経済学においてともに重要なものであったことから、経済投票(Economic voting)として、50年以上の伝統のもとに研究が続いてきました。
本書は、「日本の経済投票とはどのようなものか?」と問いました。その問いに対して、日本の経済投票を考えることで、日本人の投票行動の一形態を明らかにできるだけでなく、一党優位体制という政体の特徴も説明できる可能性がある、との答えを示しました。
この答えを示すにあたって、本書は、(1)経済投票における不平の非対称性、(2)党派性に動機づけられた推論、(3)不平の非対称性の党派間での非対称という3つのカギとなる説明を使って、日本の経済投票にアプローチしてはどうか、と提案しました。1960年代から2020年代の世論調査データと新たに収集した実験データから、日本の有権者は他国に比べて経済状況の悪化に反応し、その傾向を強めていることが明らかになります。「不平の非対称性」といわれるように、日本の有権者は、経済状態の良化よりも悪化に鋭く反応し、与党支持者であっても、経済状態が悪化すれば与党への支持から離脱していました。にもかかわらず、政権交代が起こり難い背景に、「経済の悪化に反応する与党支持者と無党派、反応しない野党支持者」というメカニズムを備えてきたことを示しました。経済状態が悪化しても、野党支持者はあまり経済状況に反応せず、与党支持や与党投票から離脱した有権者が選ぶ対象も野党ではありませんでした。経済状況に野党支持者が反応しない、与党が見限られても野党が選ばれない歴史を繰り返してきたことを、本書では「不平の非対称性の党派間での非対称」と呼び、それが一党優位体制の基底をなしているのではないか、と論じました。
こうした本書を、法政策共同研究センター・文理融合セクションの研究成果として、公表させていただくことができました。文理融合セクションでは、法学、政治学、及び経済学の分野で、ますます重要性を増す定量的データによる実証分析の研究教育が進められています。本書も、セクション内の協力研究員からの専門的な助言の数々によって、多くの改善を経て出版することができました。私自身は、公共政策の講義・演習を担当する者として、今後は政策効果とそれが市民に波及するメカニズムについて、幅広く研究教育を進めるつもりです。それが、本書に続く研究成果となることで、今回の出版助成に応えていければと思っています。
著者略歴
大村華子(おおむら はなこ)
現職:京都大学大学院法学研究科教授
略歴:1980 年生まれ。2011 年、京都大学大学院法学研究科博士
後期課程修了、博士(法学)
研究分野:政治学、公共政策、政治経済学、政治行動論。著作に,『政治行動論─有権者は政治を動かせるのか〔新版〕』(共著,有斐閣,2025 年);『日本のマクロ政体─現代日本における政治代表の動態分析』(木鐸社,2012 年)など
ケント・ローチ(土井真一・松本哲治編訳)『人権保障と救済』(信山社、2025年)
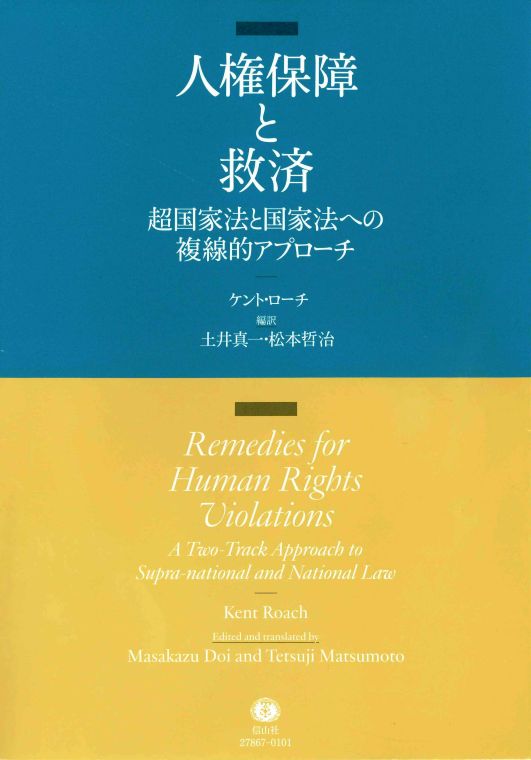
翻訳書紹介
本書は、ケンブリッジ・憲法研究叢書の1冊に収められているケント・ローチ教授の著書 Remedies for Human Rights Violations: A Two-Track Approach to Supra-National and National Law(Cambridge University Press, 2021)の全訳です。
著者のローチ教授は、現在、トロント大学法学部教授として、刑事法等の授業を担当され、国際的に活躍するカナダを代表する憲法・刑事法学者です。
本書は、ローチ教授が、その博覧強記に基づいて、超国家的な法及び国家法の両領域にわたって、人権侵害に対する救済の最新の状況を紹介するとともに、プロセス法学等に関する深い学識を踏まえて、救済における複線的アプローチの採用を提唱するものです。
英米法において、「救済」は重要な意義を有して来ました。Marbury v. Madison事件判決(5 U.S.〔1 Cranch〕137〔1803〕)において、ジョン・マーシャル合衆国最高裁判所長官は、「市民的自由の本質は、まさに、すべての個人が、侵害を受けた場合にはいつでも、法の保護を請求することができる権利に存する」とした上で、「合衆国政府は、人の政府ではなく、法の政府であることが強調されてきた。もし法が既得の法的権利の侵害に対して何らの救済も与えないとするならば、必ずや、この高貴な称号に値しないことになってしまうだろう」と述べています。権利、とりわけ人権あるいは憲法上の権利の侵害に対しては、何らかの救済が与えられなければならないとする法的確信は、英米法の伝統に深く根差すものです。
しかし、他方において、現代における制度的・構造的課題から生じた人権侵害に対しては、伝統的な司法的救済だけでは、十分に対応できない事態が生じています。こうした課題については、1970年代頃から、アメリカを中心に、いわゆる公共訴訟あるいは構造改革訴訟に関する問題として論じられており、わが国においても比較的早い段階から紹介されてきましたが、違憲審査に対して必ずしも積極的でなかった判例の動向もあり、その関心は理論的なものに留まりました。
しかし、21世紀を迎え、グローバル化が進展し、わが国の価値観やライフスタイルの多様化が進むとともに、統治機構改革の一環として司法制度改革が取り組まれる中で、最高裁判所による違憲審査が活性化してきています。それに伴って人権の実現のために積極的な判断手法が実務上も展開し始めています。
本書は、このような考察のために、多くの有益な示唆を与えてくれます。第1章において、リーガル・プロセス学派、公共訴訟論及び対話的司法審査論など、救済に関わる現代の法理論が俯瞰的に検討され、救済の重要性とその複雑な課題が明らかにされた上で、第2章において、個別的及び制度的救済に対する複線的アプローチという、ローチ教授の独創的な理論が示されます。そして、それ以降の章において、仮の救済(第3章)を含めて、人権を侵害する法律に対する救済(第4章)、損害賠償(第5章)、宣言的判決・インジャンクション・宣言的判決プラス(第7章)などの多様な救済手法や、刑事訴訟(第6章)、社会的・経済的・文化的権利(第8章)及び先住民族の権利(第9章)などの領域における救済の問題が詳細に論じられています。
このような本書の公刊のために、京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センターより多大な助成をいただいたことに厚く御礼を申し上げるとともに、本書が、人権保障と救済を考える上で、憲法、行政法、民事・刑事手続法及び国際人権法の研究者や法律実務家にとって指針を与えてくれることを願っています。
著者紹介
Kent Roach
現職:トロント大学法学部教授
略歴:1987年にトロント大学でLL.B.、1988年にイエール大学でLL.M.の学位を取得した。 2002年にカナダ王立協会のフェローに選出されたほか、カナダ勲章(2015年)、カナダ自由人権協会による自由賞(2017年にクレイク・フォーシーズ〔Craig Forcese〕教授と受賞)、モルソン社会科学・人文学賞(2017年)など多くの受賞歴がある。
主要著作
The Canadian Charter of Rights and Freedom(7th ed., Irwin Law, 2021)(共著),Constitutional Remedies in Canada(2nd ed., Carswell, 2013)、The Supreme Court on Trial(Irwin Law, 2016)など
編訳者紹介
土井真一(どい まさかず) 京都大学大学院法学研究科教授
松本哲治(まつもと てつじ) 同志社大学大学院司法研究科教授