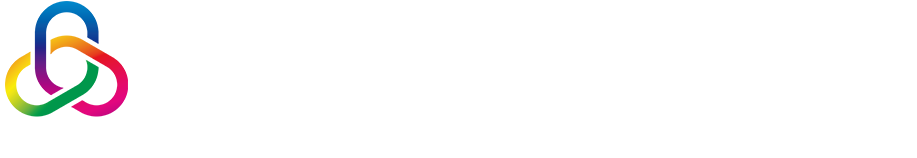海外派遣
概要
本センターでは、国際的研究を行う能力・意欲を持つ研究者を養成するため、若手研究者(助教・大学院生等)に対し、在外研究のための渡航費助成を行っている。
2024年度短期在外研究助成 概要報告
明海輝(D1)・イギリス
概要
本渡航の目的は、日清戦争の講和過程における日本外交の解明に資する史料をイギリスで収集することであった。日清戦争当時のイギリスは、香港での軍事拠点や上海での経済利権を有していたため、日清戦争の動向を注視しており、日本外交に関する情報も積極的に収集していた。実際、日本でも閲覧可能なイギリスの史料を分析すると、日本の外交文書や私文書では十分に触れられていない日本外交の姿が描かれていることが判明した。そこで、イギリス現地の史料館を訪問し、日本では閲覧できない史料を活用することで、従来の研究を更に発展させることが可能となると考え、イギリスでの史料調査を計画した。
本渡航において計画した史料調査先は、①The National Archives、②University of OxfordのBodleian Libraries、③National Library of Scotland、の3カ所であった。具体的には、①ではイギリスの外務省文書及び海軍省文書、②では日清戦争当時にイギリスの外務大臣を務めたKimberley及び大蔵大臣を務めたHarcourtの私文書、③では当時イギリスの首相を務めていたRoseberyの私文書、をそれぞれ調査する計画であった。
成果
前項で記した3カ所の史料調査先を訪問し、非常に多くの史料を収集することができた。本項では、それぞれの訪問先で収集した史料の概要、及び印象に残った史料について記すこととしたい。①では、日本での閲覧が困難な史料を中心に閲覧した。一方、日本で閲覧が可能な史料についても、日本ではマイクロフィルムでの閲覧に留まり現物を利用できるわけではないので、時間が許す限り収集を行った。その中では、史料の現物を可能な限り利用することの重要性を再確認させられる場面が複数回存在した。例えば、現物を確認することで、史料にカラーのペンを利用した書き込みが存在することを認識できるが、白黒のマイクロフィルムで閲覧する場合にはそうしたカラーの書き込みを判別することはできないのである。
②では、KimberleyやHarcourtの私文書の中で、外交関係者との書簡を中心に収集を行った。外務大臣であったKimberleyの私文書には、各国の駐英外交官との往復書簡も多く残されており、その中には日本の駐英外交官のものも一定数含まれていた。こうした書簡は、日本の史料には記録があまり残されていない、日本の在外外交官が任国政府に対して行った外交活動の実態を示すものであり、日本外交の解明に大きく貢献するものであると考えられる。③では、Roseberyの私文書の中で、日清戦争期の書簡を幅広く収集した。KimberleyやHarcourtといった人物の書簡も勿論多く存在したが、日本人留学生との往復書簡が存在し、その中では日清戦争の講和問題に触れられていることが非常に印象的であった。
井戸田耕二(D2)・ドイツ
概要
ドイツ・ケルン大学(Universität zu Köln)の刑法・刑事訴訟法研究所(Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht: ISS)において約一か月間滞在し、文献調査、および現地の研究者との交流を通じて、博士論文執筆のための資料収集を行う。
成果
1. はじめに
私は、刑法を専攻し、塩見淳教授の指導のもと、犯罪の成立時期として重要な意味をもつ「実行の着手」について、ドイツを比較法の対象国として、歴史的経緯、学説、裁判例を含めて研究し、現在、博士論文の執筆に取り組んでいます。その過程で、ドイツにおいて資料を収集し、多くの研究者と面談するなど、広い意味での現地調査が必要だと強く考えるに至りました。そして、この度、塩見教授の推薦を受け、法政策共同研究センター「短期在外研究に係る旅費の支援」制度に採用され、2025年1月16日から2月17日まで、ドイツ・ケルン大学の刑法・刑事訴訟法研究所に滞在し、短期在外研究に従事しました。
私を受け入れてくださったのは同研究所のクラウス・クレス教授・博士(Prof. Dr. Claus Kreß)です。クレス教授は、2018年に、約半年間、本学法学研究科に招へい教授として滞在され、当時法学部生であった私は教授の授業に参加し、その後も折に触れ助言をいただいてきました。
滞在中は、研究所内にある共同研究室の大きな机をお借りし、大学図書館や食堂(Mensa)の利用証、大学閉館時にも入館できる許可証までいただき、大変素晴らしい環境のもと、朝から夜まで研究に没頭することができました。クレス教授の秘書であるタニヤ・リーゼ(Tanja Liese)さんには、多岐にわたって、私の研究が成果を挙げられるよう、常に配慮していただきました。
また、現地では、私の法学部生時代からの同クラスの友人であり、本学法学研究科 博士後期課程に在学中で、かつ現在はケルン大学にてクレス教授のもとで博士論文の完成を目指している河合慶一郎君(国際法専攻)が迎えてくれ、公私にわたって大変お世話になりました。
2. 文献調査
短期在外研究における私の目的の一つである文献調査については、渡航前に期待していた以上の成果を挙げることができました。研究所はケルン大学の中心的な建物である本館(Hauptgebäude)内にあり、研究所の図書室は、研究所と場所的・機能的に一体化しており、必要に応じて、すぐに適切な本を参照することができました。また、法学部の図書室も同じ建物内にあるうえ、本館と道路を挟んだ向かいの建物には全学の巨大な図書館もあり、文献へのアクセスにおいて大変優れた環境でした。
さらに、特筆すべきと思われるのは、オンライン文献の充実さで、大学内のネットワークからアクセスできるオンライン文献は多岐にわたり、研究室に居ながらにして必要な文献参照がすべて足りることも少なくありませんでした。
このように、毎日集中的に、学術論文、体系書、コンメンタール、裁判例原文、裁判例評釈などの文献を読みふけることで、ドイツにおける未遂論の展開と現状について、多くの知識を得、理解を深めることができたように思います。
加えて、現地では日本では入手困難な書籍も購入することができ、帰国時には、それらを携え航空会社の重量制限いっぱいの書籍(約40冊)を持ち帰ることができました。
3. 現地の研究者との交流
私の短期在外研究のもう一つの目的は、現地の研究者との交流でした。もっとも、これについては私のドイツ語能力の乏しさや、期待通り研究者の方々にお目にかかれるかどうかなど、出発前の不安も大きかったのも正直なところでした。しかし、こちらについても予想を遙かに上回る成果を挙げることができました。
研究所では、スベニヤ・ラウベ博士(Dr. Svenja Raube)が私のサポート役として様々な質問に答えてくださり、さらに、共同研究室で同室であったクリスチャン・ケアケス(Christian Kaerkes)さん、ツェイダー・カパロフスカ(Ceyda Kaparovska)さんには、私の拙いドイツ語に根気よくつきあってくださり、毎日のように私の素朴な疑問に答えていただき、日本で研究していたときから抱いていた多くの疑問をこの機会に解消することができました。
研究所に隣接し、同じくクレス教授が率いている国際安全保障法研究所(Institute for International Peace and Security Law: IIPSL)の談話室には、毎日の昼食時にはかならず顔を出すようにしていました。ここでは、研究者の皆さんがめいめい昼食を持ち寄って、食事をしながら楽しい雰囲気の中で多くの会話がなされ、ここでのドイツ語は私にとってはとても難解なものでしたが、学術的なことから社会問題まで、様々な話題について研究者の皆さんの率直な意見を伺うことができました。この研究所の皆さんは、まるで一つの大きな家族のような様子で、大変あたたかい雰囲気の中で滞在することができました。
そのうえ、研究会や講演会等の大学内のイベントにも積極的に参加させていただき、過去に私が日本で検討していた学術論文の著者に直接お話を伺えるなど、ここでも貴重な経験をすることができました。
4. その他、数々の貴重な経験
現地での成果は以上のような事前の研究計画の範囲には留まりませんでした。私が現地を訪れた1月中旬は、まだケルン大学の冬学期の授業期間中で、クレス教授のご厚意で、数多くの講義やゼミナール、さらには博士論文の中間報告としての意味合いがあるコロキウムなど、多くの授業に出席する機会に恵まれました。
とりわけ、日本で学んでいたドイツ刑法の授業を実際に体験できたこと、ゼミナールで多くの皆さんのハイレベルなプレゼンテーションを聞けたこと、博士論文への取り組み方について直接見聞できたことは、大変貴重な経験となりました。クレス教授の授業は、大人数が参加する講義でも常に受講生に問いを投げかけ、かつ質問を受け付ける双方向的なもので、積極的に手を挙げて発言の機会を求めるドイツの大学生の学びに対する姿勢にも感銘を受けました。
また、研究所で知り合った友人に食事に招待してもらったり、休日に一人で街中を歩いたりと、毎日が充実しており、あっという間に過ぎ去った一か月でした。
5. 研究成果の活用
今回は、主に過去20年の比較的新しい議論についての調査を重点的に行い、その範囲では、目的をほぼ達成することができました。これらの研究成果は、これからさらに詳細に内容を検討して整理しなければなりませんが、近い将来、私の博士論文にかならず生かせるものと確信しています。ただ、やはり一か月間という滞在期間は短く、私の博士論文ではさらに古い議論も詳細に検討することが必要なため、まだ必要な調査も多く残っています。もし機会に恵まれれば、もう一度このような在外研究の機会を得、残りの調査が行えればと、今は将来に向かって夢を描いているところです。
末筆になりましたが、このような機会をお与えいただいた法政策共同研究センター、およびクラウス・クレス教授・博士はじめケルン大学の皆さまに、心より、深く感謝を申し上げます。
川瀬朗(特定助教)・アメリカ
概要
今回の渡航の目的は、2025年3月2日~5日にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴにて開催された国際関係論に関する大規模な国際学会、International Studies Association (以下ISA)の年次大会に参加して、研究課題に係る情報収集を行うことであった。
渡航者の研究課題は、経済安全保障の分脈で多くの関心を集める半導体のサプライチェーン管理をめぐり、アメリカの同盟国であるミドルパワーの国々がいかなる政策決定を行うのかを、国際政治経済学の視覚で分析するものである。経済安全保障に係る問題の一部としての半導体サプライチェーン管理については、国際政治経済学や、より広く国際関係論の研究者からも多くの注目を集める一方、日本国内の学会の議論は政策論がその中心を占めており、国家の安全保障に責任を負う政府がいかに市場アクターと対峙して政策決定を行うのかという政治過程に関する議論は希薄なままである。
これに対してISAをはじめとする国際学会においては、多角的な視点から半導体サプライチェーン管理をはじめとする経済安全保障について議論が交わされている。ISAは国際関係論に関する学会としては世界最大規模であるため、今般、研究大会への参加を通して多くの学術的知見に触れることを目指して渡航した。
成果
大会への参加を通して、期待通り多くの学術的知見に触れることが叶った。以下、今回の渡航で獲得した知見を3点に整理して報告する。
第一に、地政学(Geopolitics)に関する議論との関係である。今回のISAでも、””geopolotics””を題材としたパネルは多く設置されており、半導体に関する問題を含む様々な地政学的イシューに対する関心の高さを再認識した。他方、その多くは昨今の動向の追跡にとどまるものも多く、理論的検討の希薄さ、逆に言えば自身の研究の意義を感じる機会ともなった。
第二に、貿易政治(Trade Politics)研究との関係に関する事柄である。自身の研究は貿易政治研究の一環として行っているため、当該分野の先端的議論には強い関心があった。実際参加したパネルでは、貿易政策の形成過程における企業の役割に関する議論が多数報告されていた。この際、特に若手研究者は企業レベルのミクロなデータを扱うことに長けており、多くの刺激を受けた。ただし、それらの先端的技法から得られた知見を近年の地政学的議論と結びつけたものは多くなく、この点から、自身の研究の貢献の可能性を認識することとなった。
最後に、研究遂行における研究体制に関する事柄である。自身の研究は共同研究として行っていることもあり、海外の研究者の共同研究のマネジメントの様態は従前より気になる事柄であった。実際にいくつかの共同研究の報告を聴く中で、分業のやり方等につき多くの学びを得た。
以上のように、今回の渡航では多くの情報収集を行い、また今後の自身の研究に繋がる刺激を得た。渡航者は、2025年7月に別の国際学会で今回の渡航計画にある内容の研究報告を行うことが決定している。当該報告を良いものとするという観点からも、今回の渡航は貴重な経験となった。
佐藤悠広(特定助教)・イタリア
概要
土井翼准教授(一橋大学)が現在留学しているフィレンツェ大学を訪問する。訪問の目的は主に次の2つである。
第1に,主に申請者の博士論文について,ベルナルド・ソルディ(Bernardo Sordi)教授と意見交換を行う。申請者はドイツ法を比較対象として博士論文を執筆したが,ドイツを含むヨーロッパの近代公法学史を専攻するソルディ教授からは有益な助言をいただけると考えられる。
第2に,行政法に関するイタリア語の文献収集を行う。申請者は今後フランス法または/およびイタリア法を研究対象とすることを検討しているが,とりわけイタリア語文献は日本では入手しづらいものが多いため,幅広い領域の文献を収集する予定である。
成果
申請者の博士論文についてソルディ教授と英語で意見交換を行った。「附款」概念は解釈論上不要であるという博士論文のメインの主張についてはおおむね賛同いただけたが,「行政裁量」の定義にあいまいさが残っているという指摘もいただいた。また,「附款」をappendixと英訳するのは適当でないと指摘され,より適切な訳語についても議論を行うことができた。
フィレンツェ大学の図書館では多くの文献を収集した。イタリアでは「辞書」(人名辞書,用語辞典等々)の文化が成熟しており,日本におけるよりも必要文献・関連文献を探しやすいように感じられた。
以上のほか,フィレンツェ大学の講師にお誘いいただき,裁判傍聴をする機会を得た。民事裁判が一切非公開であること,民刑事裁判に比べて行政裁判が極めて少数であること等,日本の裁判との異同を学ぶことができた。
芝池亮弥(D2)・スペイン
概要
スペインのマドリードにて行われるThe International Society of Public Law(ICONS)の年次大会に参加する。ICONSは、公法の国際的な学会であり、情報収集・研究者同士の意見交換を行う計画である。
今年のICONSのテーマは、「公法の未来:レジリエンス、持続可能性、AI」となっている。昨今AIの急速な進歩により、法的・倫理的・社会的に深刻な問題が起こっている。そのような中で公法が果たすべき役割について本大会では議論される。
申請者は現在、サイバーセキュリティという社会問題に対して、公法が果たすべき役割について研究している。AIの発展により、サイバーセキュリティの分野においても、AIへの攻撃をどのように防ぐかといったことや、逆にAIに攻撃を行わせるといったように、問題が複雑化してきている。また、サイバー攻撃を100%防ぐことは不可能であり、レジリエンスへの着目も重要である。そのような中で、本大会のテーマは自身の今後の研究に役立つと考えられる。
成果
今回のメインテーマであったAIに関するセッションが多数あった。AIによる差別について、AIの製造過程に着目して解決を目指すセッションや、サイバー空間における人権保護について、国レベルと地方レベルが協力することで、より強固に人権を保障できると主張するセッションなどがあり、様々な観点から学びがあった。その一方、日本でもよく行われている議論も多く、日本の法学の議論水準の高さを改めて実感した。
各国から人が集まるため、「比較法」に関するセッションも多数あった。一般に日本において「比較法」と言うと、ある一国と緻密に比較を行うことが主流であると考えられるが、どの「比較法」のセッションにおいても世界中の国を対象に、データ分析を行うというものであった。たとえば、憲法改革と、民主化度・人権の保障度合い・経済成長などとの関係について、データを用いて議論がなされた。このようなことは日本ではあまり行われておらず、新しい視点を得ることができた。
また、ICONSでは若手の交流セッションや懇親会も用意され、様々な国の人々と交流することができた。特に、サイバー空間における人権保護について発表したグループとは、自身の研究テーマについて、議論することができた。
藤原いお(D1)・イギリス、アイルランド
概要
報告者の博士論文のテーマは、「18世紀イギリスにおける土地改良言説と名誉革命以降の国制の正統化の原理との関係性」である。本研究は、18世紀英国の諸言説を分析し、名誉革命体制における「国制の正統性」の論理構造を明らかにする政治思想史研究である。そのため、当時の言説空間のあり方を解明し、論争の焦点を明確化する思想史的な言説研究の方法を採る。この手法の効果として、現代では既存の学問分野に収まらないため、傍流として扱われてしまうものの、当時の言説空間では力をもっていたテクストを再発見し、研究主題に適切に位置付けることが可能となる。こうした言説研究では、その性質上、一次文献を大量に渉猟する必要がある。本計画では、大きく分けて三種類の資料を調査する予定である。
A. 18世紀型国制論の発生段階である名誉革命前後(1700年前後)の言説
B. 名誉革命擁護が再燃した1790年前後の言説、フランス革命初期論争
C. 土地改良が喫緊の課題とされていた18世紀アイリッシュの言説
18世紀イギリスの刊行物は、書籍化されていないもの(パンフレット等)についても、ECCO(Eighteenth Century Collections Online)等のデジタル・オンライン・アーカイブに相当量の収録がある。これら国内においてもアクセス可能なものは既に分析を開始している。しかし、本研究に必要な資料は、いまだデジタル化されていないか、現地でのみ閲覧可能なマイクロフィルムに収録されている場合も多い。
今回の調査では、Trinity College Dublin、Marsh’s Library、National Library of Ireland、The Brirish Library(London)の四機関を訪れる予定である。
成果
上記の計画は達成された。8/23-9/5まではロンドンにて大英図書館での資料調査を行い、9/5-9/19まではダブリンにてNational Library of Ireland, Trinity College Dublin, Marsh’s Libraryでの資料調査を行った。一次文献・二次文献を合計して5000-6000枚ほどの写真撮影をし、11月中に整理を終えた。12月現在分析中であり、2月ごろには分析が終わる予定である。その成果は上記のテーマに則した論文としてまとめたい。
上記のA-Cの資料調査がスムーズに進んだため、くわえて修士論文で扱ったダブリンの演劇論争についての資料も見ることができた。こうした成果を生かして、報告者はダブリンの演劇論争について、一次文献の翻訳を企画中である。
図書館の閉館日や閉館時間などには、18世紀関連・政治史関連の展示のある美術館、博物館などを訪問した。また、滞在地としていたダンレアリ(ダブリン)の図書館では、アイリッシュのクェイカーについての展示が充実しており、報告者の関心のあるエドマンド・バークとクェイカーのコネクションについての展示を見ることができた。
また、資料調査を初めて行った経験をもとに、「資料調査ことはじめ」というタイトルで資料調査のハウツーを研究会にて報告した(11月・八王子大学セミナーにて)。今後海外資料調査を実施する大学院生・大学生の役に立てればと思い、その際のスライドをresearchmapの資料公開のページにて共有した。報告者は渡航直前に重度の捻挫をしてしまい、全治一ヶ月の期間とこの調査旅行が重なってしまった。渡航中は常に松葉杖や歩行器具を利用していた。慣れない状態によって機動性が下がったが、宿をバリアフリーのホテルに変更するなどして対応し、上記の計画を達成することができた。ただし、ダブリンのホテル価格が高騰している事情から、当初の予定より予算が嵩んでしまった。その分は科研費から補った。
吉川聡美(特定助教)・ドイツ
概要
今回の在外研究の目的は、(1)コンスタンツ大学において、ドイツの第三者評価制度に関する文献収集を行うこと、(2)ドイツの著名な公法学者の一人でもあり、ドイツ・EUの第三者評価制度研究の第一人者でもある、ハンス・クリスチャン・レール教授(コンスタンツ大学)にインタビュー調査を行うこと、(3)昨年度の若手短期在外研究で親しくなった助手と再び研究交流の機会をもつこと、である。
(1)日本国内においては、ドイツ行政法の総論的な文献や主要な参照領域の文献は存在するものの、個別制度に関する最新の文献に関しては国内図書館に所蔵されているものはわずかである。また、昨年度の若手短期在外研究では滞在時間が極めて短く限定されており、図書館での文献調査に充てられる時間がほとんどなかった。今回の在外研究では、研究課題に関連する文献・資料の収集を行う。
(2)ハンス・クリスチャン・レール教授はドイツ公法における著名な研究者の一人でもあるとともに、製品安全法等を通じた評価制度に関する分析を行う著作があるなど、第三者評価制度研究の第一人者でもある。彼にインタビュー調査を行い、ドイツにおける第三者評価制度の現在の議論状況を理解する。
(3)昨年度の若手短期在外研究において、コンスタンツ大学で公法学を研究する助手と研究課題に関する意見交換を行った。今回の滞在でも再び交流の機会を持つことで、日独の若手研究者の相互理解を深めるとともに、継続的な交流の機会を得るための基礎とすることを目指す。
成果
(1)につき、日本国内では所蔵されておらず、オンライン上でもアクセスができない文献を多数収集することができた。特に、ドイツの州レベルでの行政上の問題に関して各州ごとに発行されている雑誌や、ドイツの博士論文が収録された書籍、ドイツの食品法上の制度に関して実務家が書いた文献など、自身の研究課題にとって必要不可欠だが、日本国内には所蔵されていない文献を多数収集するとともに、それらの文献において参照されていた文献のうち、まだ自身が把握していなかったものも複数確認することができた。これによって、自身の研究課題に対するリサーチが大きく進んだ。
(2)につき、レール教授へのインタビュー調査を通じて、現在のドイツの第三者評価制度において、評価基準がどのように作成されているのか、それらがEUの指令・規則等の他の規範とどのような関係にあるのかについて、改めてドイツの議論の現状と公法学研究者の認識に触れることができた。それは、第三者評価制度における分析の視点をより明確化することにつながっただけでなく、ドイツにおける議論を日本での議論でどの程度参照することができるか、という参照可能性と限界の問題について改めて考える機会にもなった。
(3)につき、コンスタンツ大学の助手と研究に関する意見交換を行い、ドイツ行政法学における最新の議論状況を知るとともに、彼らの研究から自身の研究に対して示唆を得た。また、助手が行っている講義にも参加し、ドイツの大学における講義の様子を体験することができた。この体験は、自身が今後教育活動をしていくうえで参照すべき価値のある、非常に貴重で有意義なものとなった。
吉原雅人(特定助教)・イタリア(ミラノ)
概要
本研究の主目的は、社会存在論が法哲学、とりわけ法概念論と呼ばれる分野に与えるインパクトについて検討するため、11月にイタリア・ミラノ大学で開催される社会存在論と法哲学のワークショップ(Philowson Workshop)に参加することであった(申請時にはワークショップでの報告を予定していたが、公募枠が競争的であり報告なしでの参加となった)。H・L・A・ハートの法理論に代表される現代法概念論とJ・R・サールの制度の哲学をはじめとする分析的社会存在論はそれぞれ、ルールや制度、社会集団の実践といった同様の概念や現象に対する視点を共有しながら、微妙に異なる理論化を試みてきた。実際に、法を社会的人工物として捉える理論など、社会存在論の知見を参照する法哲学研究はここ10年ほどの一大潮流をなしており、この流れを受けて開催されるのが、1st PHILAWSON WORKSHOP: Contemporary Views on Social Ontology and Philosophy of Lawである。このワークショップは、「社会存在論と法哲学の間の深いつながりについて理解を深め、異なる学問分野でありながら収斂しつつあるこれらの学問の交差点における知の発展に貢献することが目指す」ものであるため、Francesco Guala やAndrei Marmor などと社会存在論の議論が法哲学に対してもつ含意を議論する目的で、2日間のワークショップ参加と、前日のAndrei Marmorのレクチャーへの参加を計画した。また、前後各2日間を、現在精力的に研究成果を上げているイタリアの社会存在論・法哲学研究者の著書など、イタリアでのみ流通している文献の調査等にあて、イタリアの社会存在論と法哲学の状況を把握する計画を立てた。
成果
ワークショップでは、Andrei Marmor による法と芸術の形而上学的グラウンディングに関する共通点についての報告や、ケルゼンやハートの法理論の社会存在論的再構成についての報告がなされた。また、分析的共同行為論を法哲学に適用する際の参照点として、現象学的法哲学で知られるアドルフ・ライナッハの理論に言及する研究が多く見られた。これらの議論や自身の理論について、コーヒーブレイクやワークショップ後の懇親会において報告者と議論する機会を得た。とくに、Zuzanna Krzykalska (Jagiellonian University)とは、法の形而上学的グラウンディングと構成的ルールの関係について議論を交わし、(サール的な意味での)構成的ルールは具体的な法的対象における形而上学的グラウンディングの本質的要素ではないという点について合意に至ったほか、ポーランドの法哲学の議論状況について教示いただいた。彼女の既刊論文において示唆されている形而上学的グラウンディングに基づく法的事実の説明は、申請者の研究との関連で非常に重要な位置を占めている。この議論での成果は、法という社会種の形而上学的グラウンディングによる分析を提示する2025年の国際学会(Social Ontology 2025)での報告に反映される。さらに、文献収集においては、Bruno Celano や Giorgio Pino といった現代のイタリア法哲学の代表的論者の著作や、Luigi Ferrajoli の憲法理論に関する著作を調査し、現代イタリア法哲学の議論状況について、一定程度理解を深めた。
陳春松(特定助教)・台湾
概要
私は現在、第二次世界大戦期における中国政府の指導者である蔣介石の外交政策について研究を行っている。この研究を進めるためには、彼の日記が最も重要な資料の一つである。日記の原本は、元々スタンフォード大学附属フーバー研究所に収蔵されていたが、2023年9月に台北の国史館に移管された。蔣介石日記の他、国史館は多数の資料(蔣介石の個人資料集『蔣中正総統文物』、蔣介石の息子である蔣経国の日記など)をも保管している。
また、同じく台北に位置している中国国民党党史館も多数の蔣介石関係・国民党関係の資料を保管している。これまで私は、日記の要点を抜粋した各種史料、関連公私文書、新聞雑誌などを用いて研究を進め、その成果を博士論文「蔣介石の外交戦略と日中戦争 1937―1941」として提出してきた。しかし、今後さらに研究を深化させるためには、これまで先行研究で十分に使われてこなかった台北の国史館および中国国民党党史館所蔵の一次史料を調査・活用することが不可欠である。
そのため、この度は本助成金を十分に活用して、15日間の滞在によって、台北の国史館および中国国民党党史館でなるべく多くの資料を収集しようと考えている。具体的には以下の通りに計画している。
1) 国史館:日中戦争期(1937-45年)を中心とする蔣介石日記・蔣経国日記、『蔣中正総統文物』の閲覧・精査
2) 中国国民党党史館:蔣介石関係・国民党関係資料の閲覧・調査・筆写
成果
1、国史館:2024年3月29日以降、国史館に収蔵されている蔣介石日記および蔣経国日記の一部(蔣介石日記「1917年ー1920年」、蔣経国日記「1937年ー1938年」)は国史館の閲覧室にて閲覧することができるようになった。そのため、台北に滞在中に6回にわたって国史館に赴き、蔣介石日記および蔣経国日記を閲覧・精査した。
2、中国国民党党史館:博士論文の中では、日中戦争勃発から太平洋戦争勃発までの時期を取り上げ、蔣介石の外交戦略を再検討する。主に蔣介石と英米、ソ連、日本の関係を中心に分析を展開している。しかし、もう一つの大国であるフランスに関する考察は少なく。これは博士論文の一つの不足だと言える。そのため、党史館での資料調査は主に蔣介石・中国政府とフランスの関係を中心として展開した。特にシャルル・ド・ゴール(Charles André Joseph Marie de Gaulle)によるリーダーされている自由フランスに関する資料を多数収集できた。
李中雨(助教)・インドネシア
概要
10月9日に開催される2024 Indonesia-Japan International Lawyers Workshopは、インドネシア大学と京都大学が共催する合同セミナーであり、若手研究者3名がそれぞれの研究分野における国際法の最新の課題について発表し、その後ディスカッションが行われる。合同セミナーへの参加は、国内外の若手研究者から学び、視野を広げる貴重な機会となる。
本研究は、海洋法がグローバル・コモンズの保護という新たな課題にどのように対応し、徐々に発展してきたかを探求することを目的とする。具体的には、気候変動、公海漁業、および国家管轄権外区域における海洋生物多様性に関する諸問題について、法的枠組みがどのように機能し、「共同利益」をいかに確保しているかを批判的に評価する。
従って、この合同セミナーに参加することで、海洋法の専門家(インドネシア大学側の主催者および日本側の報告者の1人)の意見を直接聞き、議論を通じて多くの知見を得ることができると期待している。また、インドネシアのような海洋国家において、この特定の国際法がどのように認識され、実施されているのかを深く理解することを目指す。
成果
発表の機会は与えられなかったものの、報告を聴講し、その後のディスカッションに参加することで、インドネシア大学の若手研究者の研究関心について理解を深めることができ、大変有意義な学びの機会となった。そのテーマは以下の3点である。
1.インドネシアおよびASEAN諸国が、Strategy Trade Managementを通じて、軍民両用物資の流通をどのように規制・管理しているか。
2.インドネシア国際私法の最新の発展。特に、「真正な関係」の解釈において、有効な国籍を主要な判断基準としている点。
3.貿易と持続可能な発展のバランスの取り方、およびASEAN諸国の自由貿易協定における関連規定の現状と今後のあるべき構築の方向性。
また、京大側の若手研究者は、同年5月に国際海洋法裁判所の勧告的意見を中心に、海洋法条約第12部における海洋環境保護義務を説明した。そして、勧告的意見が紛争解決手段の一つとして、グローバル・コモンズの保護に新たな道を提供し得ることを指摘した。この点は、国家の同意の重要性が一定程度弱まっていることを反映しているとも言える。
KIM MINJUN(D2)・アメリカ
概要
本計画は、アメリカ国立公文書記録管理局館(National Archives and Records Administration)にて1970年代における日印関係に関する史料を収集することである。日印関係に関する公文書の他にも博論執筆における分析のために日本外交とインド外交に関する文書も収集することである。
これらの史料を集める目的は、申請者の研究に使うためである。申請者は、1964-1974年の日印関係を研究しており、研究のために日本側、インド側の史料はもちろん、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの英連邦諸国の史料を収集して検証しながら実証研究を行っている。しかし、米ソ冷戦史における国際関係史研究の特徴上、アメリカの視点と日印の対米関係もしくはアメリカの対日、対印の情報収集の面も無視できない。超大国との関連性も検討しないと冷戦史研究において研究意義を考察しがたい。
そのため、申請者は、実証研究の完成度を更に引き上げること、国際政治学における研究意義付けと国際政治学で重要視している諸論点を分析を行うためにアメリカのメリーランド州、カレッジパークに所在するアメリカ国立公文書記録管理局館にて史料調査に行こうと思ったのである。
成果
申請者は4月29日-5月3日、5月6日から2月8日までアメリカ国立公文書記録管理局館に訪問して自分の研究に必要な史料を収集することができた。これらは日印関係文書(インド外交、日本外交に関係する公文書)と日印対話の中での重要な安保懸案と関係のある史料も参考・実証・研究分析に使うために収集することができたのである。
これを通じて今回のアメリカ国立公文書記録管理局館における史料調査のおかげで本人の研究に必要な史料を収集することができ、本人の研究における実証性を更に引き上げることができ、研究の進行に役立った。更に超大国、アメリカの視点が分かるため、申請者の研究を国際政治学、冷戦史研究からも意義付けが用意しやすくなった。つまり、申請者が計画をしていた史料収集が成功したのである。
YANG XINKE(特定助教)・フランス
概要
報告者は、特定助教としての研究期間中に、夫婦財産に対する配偶者の権利を保護するための法理論を構築することを目的として研究を行っている。夫婦の財産が一方配偶者の名義で取得された場合、婚姻期間中、その財産の管理権限は名義人である配偶者に帰属する。そのため、名義人である配偶者が無断で他方配偶者に不利益となる処分や贈与を行うことで、他方配偶者の権利が十分に保護されない事態が生じる可能性がある。従来の裁判例では、名義人でない配偶者の金銭的な出捐については貢献として評価される一方、非金銭的な貢献については財産分与の際にのみ考慮され、婚姻期間中の財産管理権の判断には影響を及ぼさない傾向がある。それに対し、学説では、名義人でない配偶者を保護する手段として、財産分与請求権の保全や処分行為の取消しが提案されているが、これらのみでは婚姻期間中の権利保護としては十分でない。
本研究は、フランス法の学説や裁判例をも参照しつつ、名義人でない配偶者の貢献を適切に評価し、婚姻期間中の財産に対する名義人でない配偶者の権利を法的に確保するための新たな理論を模索するものである。これにより、夫婦財産制に関する法解釈論の深化を図り、現実的な問題解決につながる法的基盤を提供することを目指す。
本研究を円滑に遂行するため、夫婦財産関係に関するフランスの最新の法令や裁判例、論文を収集し、関連制度やその適用、学説の動向を把握することが必要である。京都大学にはフランス法関連の資料があるものの、夫婦財産法に関する蔵書は限定的であり、日本国内の他大学でも最新の資料の所蔵や更新が十分でないため、現地での書籍購入や資料収集が時間的、経済的に効率的と考えられる。報告者は、本支援金によって、2024年夏に訪れる予定のパリのクジャス図書館を利用し、研究に必要な資料を収集する計画である。
成果
報告者は、2024年9月11日から9月23日の間に、パリのクジャス図書館を訪問した。クジャス図書館は、予想を上回る豊富な資料を所蔵しており、滞在期間中、以下のような成果を得ることができた。
まず、フランス法における夫婦財産法の最新資料を調査し、必要な文献をコピー・スキャンすることができた。京都大学におけるフランス法関連の資料は比較的充実しているが、教科書から論文に至るまで更新されていないことが多い。クジャス図書館では、最新の体系書や専門書に直接アクセスすることができ、これにより夫婦財産法におけるフランスの最新の学説や実務の動向を把握できた。また、図書館アカウントの取得により、2010年以降の博士論文をオンラインで閲覧できるようになったことも大変役に立った。
次に、最新の資料に加えて、クラシックな家族法に関する貴重な資料も入手することができた。たとえば、Jean Dabinの『Sur le concept de famille』やDavid Cooperの『MORT DE LA FAMILLE』といった、20世紀の家族法における優れた研究を拝見し、スキャンすることで持ち帰ることができた。これらの資料を通して、フランスの家族概念の歴史的変遷を理解する上で重要な視点を得ることができた。これにより、フランス社会における家族の役割や価値観がいかに形成されてきたのかを明らかにし、日本法との比較に役立つ視座も得られた。
また、滞在期間中には、クジャス図書館でパリ第一大学(パンテオン・ソルボンヌ大学)やパリ第二大学(パンテオン・アサス大学)の学生と知り合う機会もあった。彼らとの交流を通して、現地の学生が日常的に活用している資料や、効率的な資料検索の方法についても教えてもらった。これにより、今回の訪仏が単なる資料収集に留まらず、現地の学生たちの学習手法や研究のアプローチについても理解を深める有意義な機会となった。このように、フランスで得た学びは、京都に戻ってからも大いに活用できるものであり、今後の研究活動にも大いに役立つと感じている。
最後に、クジャス図書館の閉館日である日曜日には、パリ市内の書店を訪れ、フランスの家族社会法や人類学に関する資料を閲覧することができた。書店の店主とも親しくなり、フランスにおける家族社会学の重要な研究資料について助言をもらうことができた。この書店での出会いを通じて、貴重な研究資料を知ることができたのも今回の滞在の大きな成果である。
2023年度短期在外研究助成 概要報告
河合慶一郎(D2)・フィンランド
概要
令和5年8月20日:出国…ドイツ・ケルン(自宅)→デュッセルドルフ空港→ヘルシンキ空港→フィンランド・ヘルシンキ
8月21日〜25日:Helsinki Summer Seminar on International Law 2023に参加(於 ヘルシンキ大学Erik Castrén Institute)
8月26日:帰国…フィンランド・ヘルシンキ→ヘルシンキ空港→デュッセルドルフ空港→ドイツ・ケルン(自宅)
成果
本研究は5日間の夏期講習である。1日目はLeino-Sandberg教授から権力分立の概念や国内/国際的統治機構におけるその実践について、Klabbers教授から国際機構による実際的な権力行使の記述における伝統的国際法の不備について、Tuori教授より専門家支配の正当化(正統化)可能性について、それぞれ講義があった。2日目はSormune/Gnes両教授よりEU外交におけるソフトローの多用とその正当性について、Eckes/Ankersmit両教授よりエネルギー憲章脱退問題について、講義があった。3日目はプログラムが変更となり(Sending教授が講義を行わず)、Ghavanini教授よりEU法上の権力分立における裁判所の役割について、Ankersmit教授よりEUが通商協定を結ぶプロセスについて、Klabbers教授より国際機構のアカウンタビリティについて、Koskenniemi教授より国際法が持つ国際社会の支配者のための学問としての側面について講義があった。4日目はMöller教授より伝統的権力分立における専門知の位置付け、国制(国政)において熟議が果たしうる役割とその限界について講義があった。5日目はKantola教授よりEUにおける欧州議会の役割とそのジェンダー学的研究のマニフェストについて講義あったのち、Leino-Sandberg/Klabbers/Koskenniemi各教授と受講者らが講習を振り返り、今後の課題についてそれぞれの意見を交換する機会がもたれた。
伝統的国際法学は、国際社会における権力行使の記述・分析という点においては、国家と国際機構にのみ注目してきたため、グローバル・ガバナンスの一翼を担い、影響を及ぼす諸個人(特に専門家)の役割を理論のレベルで看過し、それゆえグローバル・ガバナンスの実態を把握できていないと批判されているが、今回の夏期講習参加を通し、この伝統的国際法学の不備を補完する研究手法や思考法につき、今後の申請者の国際法研究に資する学際的知見や人脈を得ることができた。
來住南桃(D2)・台湾
概要
本在外研究では、the Asian Law Schools Association (ALSA)主催のカンファレンスに出席する予定である。同カンファレンスでは、世界各国の法とテクノロジーに関連する専門を有する研究者による講演が行われる。
本在外研究における目的は、法とテクノロジーに関する最先端の研究成果を収集することである。特に、ロボットを巡る法的課題や、ロボットと人との関わり合い(ヒューマン・ロボットインタラクション)に伴う法的問題と、それに対する解決策やあるべき法制度・法システムについて示唆を得ることを目的とする。
近時、ロボットやAI等の最先端テクノロジーの発展がめざましいところ、それに対応する法制度は未だ確立しているとは言いがたく、かようなテクノロジーを適切にガバナンスする仕組みについての議論は急務といえる。本研究では、この点に関して、本カンファレンスの参加を通じて最先端の議論を収集する。本カンファレンスには、世界的に有力な法とテクノロジー・ロボット法等を専門とする研究者がパネリストとして参加をするため、本カンファレンスへの出席により、重要な研究成果が収集できると考えられる。
また、テクノロジーの特徴として、国境を越えてグローバルに展開するというものがある。よって、法制度においてもグローバルな観点から議論をすることが必要である。他方、テクノロジーに対する社会ないし各市民の受け入れ方には各文化により相違がある可能性もあり、また各国の従来の法制度や国家制度の文脈を無視するわけにはならない。よって、テクノロジーと法を考えるに当たっては、文化的差異を念頭に置いた議論もまた、欠かせないものである。本カンファレンスでは、世界各国の研究者による研究成果の発表が予定されており、それも東アジアーヨーロッパーアメリカ合衆国と、文化的差異の大きな地域からの研究であることから、グローバルな議論への参加や、文化的差異の分析が可能であると考えられる。
また、本カンファレンスの前後に、パネリストの研究者の方々との交流や、東アジアの同領域の研究者ないし法曹実務家からなる参加者たちとの交流を行う予定である。この交流を通じて、上記研究成果の収集や、議論への参加をより深く行うほか、日本の現状を相対化して見ることにより日本の社会や法制度の現状と課題ないしグローバルな訴求点についての発見や理解を深めたいと考えている。
よって、本在外研究では、カンファレンスの出席と参加により、テクノロジーと法に関する研究成果を収集し、研究者との交流を行う計画である。
成果
本在外研究では、Asian Law School Association(ALSA)主催の国際カンファレンスに参加し、報告発表による情報収集を行ったほか、各国の研究者と交流並びにディスカッションを行った。
具体的には、来年夏に刊行予定の、『ケンブリッジハンドブック・ヒューマン・ロボットインタラクションのための法、政策、規制』の共同著者らによる発表を聞いた。発表によれば、①ロボットは様々な形、例えば医療や機械の組み立てなど特定の目的達成のためのロボット、人間とふれあい情動的つながりを生むことを目的とする(ケアないしペット)ロボット、人間と類似しAIを具現化するようなアンドロイド、宗教的役割を担う宗教ロボット、軍事ロボット、などとして現れてきているが、②これらそれぞれのロボットにはその使用に当たって異なるリスクが存在し、③また開発上・倫理上の問題もはらむ。④そこで、ロボットへのガバナンスシステムの構築が喫緊で求められているところ、⑤各国において従来の法・政策の素地は異なるうえに、ロボットと人間とのインタラクションにおいては文化差が存在することが実証的研究から明らかになっているため、⑥それらの違いを踏まえつつ、⑦他方テクノロジーは国境を越えて広がっていくので、国際的にも通用生のある枠組みを定立していくことが必要である。そして、そのためには、分野・国境を超えた研究と、多様なバックグラウンドの者がマルチステークホルダーとして関わることができるような仕組みを策定することが有用であると考えられることに関しては多くの研究者の見解の一致が見られる。
髙坂博史(特定助教)・イギリス/フランス
概要
本研究は、冷戦末期にNATOとワルシャワ条約機構との間で実施され、第二次世界大戦後では初めてとなる通常戦力の軍縮条約を生み出したヨーロッパ通常戦力交渉(CFE交渉)の立ち上げに至る国際政治過程を明らかにするものである。そのために、1986年11月から1989年1月にかけてCFE交渉の条件闘争の舞台となり、最終的にはCFE交渉の方向性を定めて交渉開始を決定した欧州安全保障協力会議(CSCE)ウィーン再検討会議を分析する。これにより、CFE交渉の中核をなすアイデア(CSCEの枠組み下に置かれること、戦力削減の対象地域を「大西洋からウラル」までのヨーロッパ全域とすること、現地査察による検証を行うことなど)がいかにして生み出され、合意されたかを解明する。
本研究は、CSCEウィーン再検討会議において主導的な役割を果たした西ヨーロッパに着目する。なかでも、西ヨーロッパの主要国として安全保障問題で大きな発言力を有した英仏二ヶ国にフォーカスする。そこで、イギリスおよびフランスのアーカイブにて公開後間もない一次史料を収集するべく、両国で1週間ずつ滞在する渡航計画を立てた。
成果
上記の研究計画に基づき、英仏二ヶ国において史料調査を実施した。両国では研究テーマであるヨーロッパ通常戦力交渉(CFE交渉)の立ち上げへと至る経緯(その議論は1986年から1989年にかけて欧州安全保障協力会議(CSCE)ウィーン再検討会議において実施された)に関する文書を閲覧した。
イギリスでは1週間滞在し、外務省、首相府や国防省などの文書を所蔵する国立公文書館にて史料調査を実施した。イギリスはヨーロッパのなかでもひときわ一次史料の所蔵量が多く、また他国に先んじて開示を進めているため、関係する膨大な文書を閲覧・撮影することができた。滞在期間中に関係する全てのファイルを見終えることは叶わなかったが、あらかじめ定めていた優先順位に基づいて主要なファイルを見ることができた。
フランスでも1週間滞在し、外務省の文書を所蔵する外交史料館にて史料調査を実施した。フランスでの一次史料の開示状況はイギリスと比べて限られていたものの、事前に開示請求を行っていたこともあり、必要なファイルを閲覧・撮影することができた。また、現地でしか見ることができない史料の所蔵状況に関するデータベースを閲覧し、今後開示請求をかけるべき文書についても目星をつけることができた。
詳細な分析は今後本格的に取り組む予定であるが、現地での調査を通じて、西ヨーロッパ諸国がCFE交渉の立ち上げ過程において大きな影響力を行使していたことが判明した。なお、研究成果は2024年1月に大学院の「国際政治学スクーリング」にて中間報告を行い、そのフィードバックを元に論文の執筆を行っている。
円安に加え、航空運賃が高騰(とりわけロシア上空の迂回を強いられるヨーロッパ線の運賃は数年前の2倍近くとなっている)するなか、若手研究者にとって海外渡航はますます厳しくなっている。このようななか、本支援は研究を継続するうえでかけがいのないものであった。このたびの支援に深く御礼を申し上げます。
髙橋侑生(特定助教)・イギリス
概要
[研究目的・内容]
本研究は、1950年代イギリスにおけるニューレフト運動(以下、第一次ニューレフト運動)が有する政治思想史的意義を解明することを目的とする。第一次ニューレフト運動とは、1957年に創刊された2つの雑誌(Universities & Left Review誌とNew Reasoner誌)を中心とした思想運動である。この運動はこれまで、カルチュラル・スタディーズの源流として評価・研究されることが多かった。これに対して本研究は、チャールズ・テイラーやアラスデア・マッキンタイアといった重要な政治哲学者が第一次ニューレフトとして舌を振るっていたという事実に着目する。それによって、第一次ニューレフトに特有の思考枠組が、彼らを介して、戦後英米圏における政治哲学の発展に影響を与えた仕方を思想史的に明らかにしたい。そのために、本研究はまず、戦後英米圏の政治哲学にかんする思想史研究の興隆という近年の研究動向を踏まえつつ、第一次ニューレフト運動の形成・瓦解過程を実証的に再構築し、その言論空間に特有の思考枠組を同定することを試みる。
[渡航計画]
以上のような思想史的解明を十全に行うためには、日本国内からアクセスできない公刊論文・記事を参照する必要があるだけでなく、運動内で交わされた未公刊の様々な文書(例えば、手紙、編集委員会の議事録、報道・広報資料、草稿)を幅広く調査する必要がある。その点、イギリス国内には、それらの史料を豊富に所蔵・公開している図書館・資料館が点在している。そこで、2024年3月16日から2024年3月24日という日程でイギリスにおける史料調査を計画した。
成果
[日程・用務先] 以下のとおり史料調査を行った。
3月17日:The British Library of Political and Economic Science (LSE)
3月18日:Bishopsgate Institute
3月19日:Bishopsgate Institute
3月20日:Bishopsgate Institute
3月21日:Bishopsgate Institute; The British Library of Political and Economic Science (LSE)
3月22日:Cadbury Research Library (The University of Birmingham)
[成果] 以下の史料を調査した。
(1)The British Library of Political and Economic Science
International Socialism誌(1960-1970)、イギリス労働党パンフレット、他
(2)Bishopsgate Institute
New Left Archive(RS1/001-024, 031, 101-102, 104)、Samuel Posters and Plans Collection(RS11/060-063)、他
(3)Cadbury Research Library
Stuart Hall Archive(Box 65, 67-71)
各館に所蔵されている史料の量に圧倒されたが、テイラーとマッキンタイアを中心に調査対象を限定することで効率的に調査を行った。結果として、1950年代イギリスにおけるニューレフトの肉声を伝える様々な史料を収集することができた。それらには、彼/彼女らがどのような関係性にあり、どのような問題にとりわけ注目し、どのような事柄について対立していたのかが示されている。今回の史料調査において、第一次ニューレフト運動を実証的に解明し、その政治思想史的意義を論じるために欠かすことのできない重要史料を大量に入手することに成功したと考えている。
村角愛佳(特定助教)・ドイツ
概要
本研究の目的は、国際法上の武力行使禁止原則の二元的理解(同原則を国家対国家的視座と人間的視座の両者から理解する)に基づいて、同原則の例外であり「国家の固有の権利」とされる自衛権を捉え直し、自衛権をめぐる議論に新たな視点を提供することである。武力行使禁止原則の二元的理解の下で核となる人間的視座とは、国籍に関わらず人間の利益あるいは価値に着目する視点である。人間に焦点を当てる視点を武力行使の分野に取り込むといっても、国家はなお現在の政治秩序における決定的な単位であり、特に武力行使は国家対国家的性格の強い分野である。特に、武力行使禁止原則の例外である自衛権は、「国家に固有の権利」(国連憲章51条)といわれるように、それ自体として価値を認められる国家が有する権利であるとされてきた。一方で自衛権をめぐる実践的問題の中には、人間的視座なくしては適切な理解ができない問題がある。そこで本研究は、一見人間的利益とは対極にあるようにみえる自衛権につき、その理論・実践の両問題を武力行使禁止原則の二元的理解に基づき論じることで、自衛権概念の再検討を行う。
渡航先のマックス・プランク比較公法・国際法研究所は、ドイツのみならず世界でも屈指の国際法研究機関であり、国際法に関する文献・資料が豊富に所蔵されている。また受入研究者(Anne Peters教授)をはじめ、国際法の専門家が多数在籍している。さらに、ヨーロッパに位置していることから、多くのシンクタンクや研究所においてシンポジウムや研究会が頻繁に開催されている。在外研究の機会を最大限に活用し、自らの見解をセミナーなどの場で発表し、理論の精緻化を図り、海外の国際法学者との意見交換を通して示唆を得て成果に繋げることを目指す。
成果
全日程にわたり同研究所で多数の文献・資料を収集した。
武力行使禁止原則の二元的理解については、同研究所のAgora Meetingにて、2024年7月10日に報告した。このAgora Meetingには同研究所に在籍する多くの研究員が参加し、活発な議論を行なった。
最近の非国家主体に対する自衛権をめぐる議論に武力行使禁止原則の二元的理解がいかに貢献するかについては、2024年10月19日に京都大学国際法研究会にて報告する予定である。本報告はドイツのケルン大学大学にて同分野の研究に携わっているRaube博士との共同報告を計画している。2024年7月3~4日にかけてケルン大学を訪問した際にRaube博士と意見交換をする機会があり、この共同報告を行う運びとなった。
さらに、2024年12月には、本研究成果の一部を含む単著(題名未定)が、京都大学学術出版会から出版される予定である。
また、毎週月曜日のMonday Meetingに毎度出席し、議題につき意見交換を行なった。この時に知り合った研究者らとは、海外セミナーへの招待や他の研究機関の情報などついてメールで教示を頂くといった形で現在まで交流が続いている。
森廣祐也(特定助教)・ドイツ
概要
申請者の研究テーマは、競争法が保護する私的利益(競争利益)の内容・性質や一般的公益との関係を分析することを通じて、我が国における行政訴訟・民事訴訟による競争利益保護の在り方を再構築することにある。上記研究を行うにあたり、ドイツにおける議論との比較・検討を行ってきたが、以下のような課題が存在している。
まず、ドイツにおいては、競争利益の保護は主として民事訴訟によって実現されることが念頭に置かれているのに対し、我が国においては、民事訴訟のみならず、行政訴訟による実現も志向されている。競争利益の保護を実現するにあたっては、行政訴訟・民事訴訟において保護される利益の共通点と相違点に留意する必要があり、そのためには特にドイツ民事法・競争法の議論についてより立ち入った分析が必要となる。さらに、ドイツにおける競争利益保護に関する議論はEU法の影響を多大に受けており、近時ドイツではEU法を前提とした上で、行政法と民事法の交錯をめぐる議論が活発に行われている。申請者の研究をさらに進展させるためには、ドイツ・EUにおける最新の議論状況の把握が必要不可欠である。
そこで今回の渡航では、コンスタンツ大学のH.C.Röhl教授が主催するセミナーに参加し、行政法・民事法・経済法の研究者との意見交換を行うことで、各領域の近時の動向を把握することを目的とする。具体的には、ドイツ・EUにおける行政法学の動向に詳しいRöhl教授、団体訴訟やクラスアクション制度をはじめとする民事訴訟制度の構築と法執行の関係を研究している Astrid Stadler教授、ドイツ競争法と民事法を研究しているJochen Glöckner教授のほか、コンスタンツ大学に所属する若手研究者(助手)との意見交換を予定している。セミナーでは、各領域の議論状況をご教示いただくとともに、今後の研究に関するご助言をいただくつもりである。
成果
ドイツ・コンスタンツ大学にて、Astrid Stadler教授、Jochen Glöckner教授、H.C.Röhl教授から、ドイツ・EUにおける競争に関する利益保護の在り方と競争法のエンフォースメントに関する議論状況についてヒアリングおよび意見交換を行った。
Stadler教授からは、まず民事不法行為法における保護規範と、行政法における保護規範の相互関係について、都市法における隣人保護に代表されるように、両者には重なり合いが認められる場面が見られるとの指摘をいただいた。その上で、競争に関する利益については、競争法規範が不法行為法における保護規範に該当するか否かで争いがあったものの、2019年のEU指令により、保護規範の該当性が肯定されたとの情報提供をいただいた。Glöckner教授からは、ドイツ競争法学における競争制限禁止法および不正競争防止法の保護法益に関する議論状況の推移と、ドイツにおける私的・公的エンフォースメントの課題について情報提供を受けた。また、不法行為法における競争に関する利益の保護について、我が国では2001年に欧州司法裁判所が出したCourage判決に言及されることが多いところ、ドイツでは同判決の後に連邦通常裁判所が出した2011年owie判決が大きな転換点になったとの指摘をいただいた。Röhl教授からは、行政法におけるエンフォースメントに関する議論の発端となったのは、2003年に出された行政裁判所によるカルテル例外許可の取消しを求める私人の訴えであるとの情報提供をいただいた。
いずれの議論も日本では十分に認識されていない問題であり、今後の研究課題として検討を進める予定である。
吉川聡美(特定助教)・ドイツ
概要
今回の在外研究の目的は、コンスタンツ大学においてドイツの大学認証評価制度に関する文献収集を行うとともに、実際に認証評価実務に携わっている大学関係者、認証評価機関関係者にインタビュー調査を行うことであった。
成果
コンスタンツ大学はドイツにおける有数の大学として、ドイツ・EUの大学制度・認証評価制度に関する文献を多数所蔵しており、日本の図書館・インターネットでは閲覧できない資料を収集することができた。また、実際に認証評価に携わっている大学関係者・認証評価機関関係者にインタビュー調査を行うことで、実際に認証評価を行う際の実務的感覚に触れることができ、それらは認証評価制度における法的課題を発見・分析する際の視点の一つとして非常に参考になった。特に、大学内部の認証評価業務担当者と、大学外部の認証評価担当者(認証評価機関)では意見の異同が様々な形で存在しており、どのような観点から分析するかということを考えさせられた。さらに、ドイツの認証評価制度の改正作業が現在行われているが、どのような形で今後改正が進んでいくのかについても、実務担当者から話を伺うことができ、最新の動向を把握することができた。今回の在外研究を通じて、形式面だけではなく、大学認証評価制度に関してより実態に即した法的分析を行っていきたいと思う。
吉原雅人(D3)・イギリス
概要
本研究は、法概念論研究において近年海外で注目されている「法の人工物理論 artifact theory of law」を中心に、法の存在構造を解明することを目的として、法の人工物理論の先駆的な提唱者でもあるイギリス・サリー大学のケネス・M・エーレンバーグ教授のもとを訪問し、著書『法の諸機能 The Functions of Law』(OUP, 2016)についてインタビューを敢行するものである。インタビューはエーレンバーグ教授と相談した上で、紹介者である慶應義塾大学助教商学部特任助教の伊藤克彦さんに同席していただき、ロンドン市内のカフェで行うことになった。
内容としては、現在、L. Burazin, K. E. Himma & C. Roversi eds., Law as an Artifact (Oxford University Press, 2018) と、L. Burazin, K. E. Himma, C. Roversi & P. Banaś eds., The Artifactual Nature of Law (Edward Elgar, 2022) という二篇の論文集が立て続けに刊行されているように、法概念論研究において注目を集めている、法の人工物理論についての議論状況についてが中心となる。具体的には、法を人工物として捉える際に問題となる哲学的機能分析への批判への応答方法や、「機能」概念そのもの、人工物の哲学を含む社会存在論(social ontology)における議論を法哲学に応用する際に障壁となる分野間の焦点の違いなどについて質問した。さらに、エーレンバーグ教授の所属するサリー大学は現在、世界でも有数の規模を誇る法哲学センターを擁する。そこで法哲学センターの研究環境についても質問した。また、インタビュー以外の日程で法の人工物理論に関連する文献についてロンドン市内の図書館で閲覧調査を行った。
成果
ここでは、インビューへの回答の中でも特に短期在外研究の成果として挙げることができるだろう内容をいくつか紹介する。まず、エーレンバーグ教授の著書『法の機能』について。彼は、法を人工物の一つの種類(ジャンル)として捉え、法という種類に共通する機能を探究すべきだと主張している。この主張について、そもそも法に固有の機能が存在するという想定がどれほど妥当なのか質問を行った。エーレンバーグ教授によれば、人工物の「ジャンル」の機能は、そこに属するとされる個々の具体例(トークン)を私たちが一つのグループ(タイプ)にまとめるときに一般化するものである。法の機能を同定するということは個々の法の機能をリストアップして一般化するということである。このインタビューでは、エーレンバーグ教授が人工物の機能帰属において作者の意図を重視する理由がより明確になった。彼は、人工物の機能が理解されるためには作者がそれを何のために作り出したかを理解する必要があり、そのために作者が人工物を通じて何らかのコミュニケーション(シグナリング)を行うと考えている。したがって、慣習法のように作者が明確でないような法の形態においては、裁判官がその法的妥当性を承認するような一連の手続きが必要であると主張することになる。私見では、この点について人工物理論を提唱する理論家の中でも立場が分かれるが、エーレンバーグ教授の立場が(著書において論じられてはいるものの)明確化されたことは一つの成果であると言えるだろう。
また、エーレンバーグ教授は、(たとえば、ブライアン・タマナハ教授が主張する)法の機能分析が過度な単純化に陥っているという批判に対して、法の機能の一般化と過度な単純化は区別するべきだと応じている。一般化は複雑さを許容するため単純化に陥るということはない。タマナハ教授が関心を持つ経験的研究の観点からはより具体的な調査が必要になるかもしれないが、哲学的には、法が用いられるさまざまな方法を特徴づけることができていれば、一般化は法の説明において要点を損なうわけではないというのが、エーレンバーグ教授の回答である。ここでの一般化と単純化の区別についてはさらなる研究が必要であるが、法哲学のような抽象的な概念的研究にとって「一般化」をどのように特徴づけるかは重要な論点であるように思われる。人工物理論への批判としては、法のように大規模な事業を、作者の意図を伝達する人工物として捉えることが過度に制限的であり、より大きな括りである「社会的構築物」として捉えるべきだという批判もある。これには、より制限の大きい概念を用いることで得られる情報量が大きくなるという応答が得られた。(ここで念頭に置かれているのは、上述した「作者の意図」である。)インタビューでは、法の人工物理論についてこれ以外にも今後の研究の展望など重要な示唆を得られる回答を多くいただいた。
それに加えて、サリー大学での研究環境についても法哲学研究を遂行する上で重要なコメントを多く頂戴した。現状、サリー大学の法哲学センターには20人程度の法哲学研究者が在籍している。これは日本ではもちろん世界的にも相当な規模のセンターである。この要因については、ロースクールと学部教育の関係におけるアメリカとイギリスの相違などに言及があった。しかし、より重要なこととして、それだけの規模で専門的背景を共有した研究者が一同に会する機会が確保されることによって、研究成果の相乗効果が見込めるという利点が(当然ながら)指摘された。エーレンバーグ教授は、「私たちは誰もスーパースターではありません。スコット・ハーショウィッツやスコット・シャピロのようなレベルの人はいないのです。ジェレミー・ウォルドロンのような大家もいません。私たちはまだ新進気鋭で、このような大所帯だからこそ、良い議論ができるのです」と述べている。このような研究環境を実際に確保することにはさまざまなハードルが存在するが、共通の背景を持つ研究者数を確保した上での議論空間の実現という考慮事項は、特に(法哲学だけに限らず)哲学・概念研究のあり方として示唆に富むものだと考える。
呉舒平(特定助教)・アメリカ
概要
以下の通り、アメリカでの学会発表および研究調査のために約3週間滞在しました。
3月8日~10日 サンフランシスコ・チャイナタウンで研究調査を行いました。
3月11日~13日 カリフォルニア州公文書館(California State Archives)で研究調査を行いました。
3月14日~17日 米国アジア研究協会(Association for Asian Studies)研究大会に参加し、研究発表・意見交換を行いました。
3月18日 ウィング・ルーク博物館(Wing Luke Museum)で研究調査を行いました。
3月19日 国立公文書館サンフランシスコ館(National Archives at San Francisco)で研究調査を行いました。
3月20日~25日 サンフランシスコ・チャイナタウンで研究調査を行いました。
今回の渡航で、アメリカ西海岸での史料収集のみならず、サンフランシスコの華僑とのインタビューも行い、在米華僑のアイデンティティに関する実相をさらに理解を深めるための材料を得ました。また、米国アジア研究協会では、世界中から集まる研究者との交流を行い、自分の視野を広げ、さらなる知見を得ることができました。
成果
サンフランシスコでは、チャイナタウンおよび近郊のサンブルノにある国立公文書館サンフランシスコ館を訪問しました。サンフランシスコのチャイナタウンでは、華僑事務を担当する中華民国の在外機構であるサンフランシスコ華僑文化教育センター(金山華僑文教服務中心)および華僑の会館を訪問し、インタビューを行いました。また、サンフランシスコ国父記念館(金山國父紀念館)所蔵の史料を収集しました。同館は、孫文の書信など、一次史料が多数収蔵されています。サンフランシスコ公立図書館チャイナタウン分館(San Fransisco Public Library Chinatown Branch)にも訪問して資料収集を行いました。同館は、アジア関係の研究や資料を多数所蔵し、サンフランシスコの華僑コンミュニティの一次史料があります。国立公文書館サンフランシスコ館は予約制で、事前に米国国立公文書館のオンライン・カタログ(https://catalog.archives.gov/)を利用してタイトルなどを確認してメールで予約を取る必要があります。同館は孫文の渡米記録や華僑に関する米連邦レベルの公的記録が収蔵されています。
カリフォルニア州州都のサクラメントにおいて、カリフォルニア州州立公文書館(California State Archives)が所蔵されているカリフォルニア州のアジア系移民関係資料を、華僑を中心に調査しました。同館所蔵資料の目録はオンライン(https://archives.sos.ca.gov/)で確認できるため、事前に同サイトでタイトルなどを調べておきました。訪問時に予約の必要がなく、カウンターで申請表を記入するのみで、身分証明の確認も特にありませんでした。史料の撮影も可能でした。州立公文書館と併設されているカリフォニア博物館(California Museum)をも訪問しました。同館はカリフォニアの華僑や日系移民に関する豊富な展示とインタビュー資料があり、一部収集しました。
シアトルでは、4日間の米国アジア研究協会(Association for Asian Studies)の研究大会に参加し、研究発表と学者間の意見交換を行いました。同会は、アジア地域研究のなかで、世界最大級を誇る学会で、世界中から集まってきた研究者との交流や、研究発表に対するフィードバックは、いままでの研究成果をさらに向上させる糧となります。大会後、シアトル・チャイナタウン=国際区にあるウィング・ルーク博物館(Wing Luke Museum)で研究調査を行いました。同館では、アジア系移民に関する史料が大量に展示され、その中に貴重なインタビュー資料も多数あります。また、同博物館にはゲイリー・ロック州知事図書館(Governor Gary Locke Library)が併設されています。図書館のサイトで目録(http://db.wingluke.org/)を確認し、同サイトで予約を取る必要があります。同図書館では、在米華僑やアジア系移民の写真、文書などが所蔵されています。
江子正(D3)・アメリカ
概要
申請者が行う研究はパリ講和会議における人種平等問題であり、同問題は日本に国際連盟委員会に提起されたが、オーストラリア首相のヒューズの反対工作およびアメリカ大統領ウィルソンの決断・拒否権行使によって失敗したと先行研究は結論つけている。しかし、こうした結論は単純化しすぎる傾向があり、申請者がこれまでオンラインで利用したアメリカ側の資料、具体例挙げるとミラー筆記(The Drafting of the Covenant)およびハウス日記(Edward Mandell House Papers, Diaries)などによって、ウィルソンの日本の提案に対して好意的な態度をすでにある程度明らかにした。しかし、これ以上の進捗、特に博論レベルの研究を仕上げるため、現地調査が必要不可欠である。
博士課程のこれまでの一年半の間に、申請者は中国、イギリス(ケンブリッジ大学の場合は短期留学も)、フランス、ドイツおよびポーランドで資料調査をし、先行研究で全く解明できなかった予想以上の成果を得ていた。現在資料整理と論文執筆に力を入れているほか、科研費が足りない状況の中で、アメリカでの短期留学、調査、学会報告を計画している。具体的には★ハーバード大学およびプリンストン大学の図書館、国会図書館、NAACPの資料館、シアトルなど(2月~4月)。さらに、アメリカでの滞在は具体的には三点にまとめられる。
①短期留学
申請者は今年イギリスのケンブリッジ大学で短期留学に行っており、すでに英米圏での留学経験を有している。しかし、英語特に会話力の強化のためにも、今のうちにもう一度北米での短期留学を計画している。現在指導教員の奈良岡先生から教えていただいた情報によると、ハウェル先生のゼミでは人種問題を研究する先輩もいて、なおさら刺激を得て、活発かつ有意義な交流が期待できる。
②資料調査
そして、短期留学の期間中、授業のない時期や、週末・休日などを利用し、アメリカにおいては頻繁に資料調査に行く必要もある。具体例を挙げると、プリンストン大学におけるウィルス大統領の関連文書や、コロンビア大学が所蔵されるV. K. Wellington Koo papers、およびアメリカ議会図書館(Library of Congress)や国立公文書館などにおいても積極的に調査を行い、先行研究で活用できなかった一次資料を収集し、解読と論文に使う予定である。
③学会報告
2024年3月にシアトルで開催されるアメリカアジア学会(Association for Asian Studies)での報告をパネル形式で申請しており、採択されるとアメリカ滞在中に同学会で報告を行い、最先端な研究動向を勉強する。そして、パリ講和会議において日本の人種平等提案を否決した際、最終判断を下したのはアメリカ大統領のウィルソンなのであり、自分の研究に関してアメリカ側の研究者からコメント・評価を得るためにも重要である。
本支援への申請が採択されると、博士課程での研究が大きく前進し、帰国した後すぐに法政策共同研究センター事務室に必要な書類・法学研究科長に報告書を提出するほか、新しい学術論文にまとめる。
成果
①短期留学
無事にハーバード大学のハウェル教授の研究室で二週間の留学を行った。同先生は日本近代史の専門家だけでなく、社会政治史的な角度から研究を行っており、人種平等提案を政治・外交史的な視点ばかりではなく、社会史的な視点も吸収し、全体像を見えるためにも、貴重な研究環境だと言える。今回は刺激を得て、活発かつ有意義な交流ができました。
②資料調査
資料調査の面では、ハーバード大学滞在中に各図書館にあるパリ講和会議関係一次史料、先行研究を積極的に収集をいたしました。そのなかにはとくに法学部図書館のDavid Hunter MIlerの日記などは一番大事な資料となる。その後、プリンストン大学にも通い、ウィルソンコレクションを収集し、ワシントン・DC、そしてシアトルにおいても議会図書館や公文書館で史料調査をした。パリ講和会議における外交官の個人文書を中心にした。
③学会報告
2024年3月にシアトルで開催されるアメリカアジア学会(Association for Asian Studies)での報告をパネル形式で無事に行った。多くのコメント・意見をいただき、これから博論執筆に大変役に立つ機会であった。
趙善涓(D2)・オランダ
概要
1月8月から1月26日までの3週間の間には、平日の朝9時20分から12時30分まで、アカデミーで提供されていた一般講義を受講する。国際法及び国際私法に関する世界の最先端の多様なテーマについて講義を受け、幅広く重要な知見を得ることである。午後には、個別セミナーを参加したり直接教授に質問をしたりすることで、自分が興味のある分野についての理解を深める。空き時間は、隣接する平和宮図書館において英文の資料収集を行い、比較法的観点からの考察をしながら修論執筆を進める。なお、ソーシャル活動とイベントを通じて、同じコースを参加する受講者たちと交流し、多角的な視点で国際平和や人権のあり方を考える。
成果
研究成果としては、まず、三週間のコースを通じて、自分の専門分野だけではなく、本来接したことのない分野について学び機会をもらい、新たな知見を広げた。今の国際社会が直面している危機や問題について、国際法がどこまで介入でき、解決策を提供できるかということに、より具体的なイメージができた。冬季コースが講義以外にも、豊かなソーシャルイベントが提供されていた。そのため、オランダ滞在期間中、現在国際司法裁判所で勤めている裁判官と直接対話したり、さまざまな大使館と特別裁判所を訪れたりしたことで、国際法分野に関する重要な司法機関及び国際機関の運用仕組みを理解できた。そして、本コースを接点として、各国の研究者や法曹、外交官、学生などと交流する機会が作られ、通常では出会えないような人と意見交換することで、自分の研究課題に対する理解をさらに深めることができた。
次に、講義がない午後や週末には、ハーグ平和宮図書館のデータベースを活用して、修士論文の調査及び研究を進めることができた。日本におけるハーグ条約の運用をめぐる課題を検討する際に、子どものために法の正義を実現できる体制を整備していくためには、欧州各国における子どもの権利を保障するための法整備の経緯や学説及び判例の状況を含めて考慮することが重要であるといえよう。それゆえ、現地で英語文献を直接アクセスして、より幅広く比較法研究の成果を取り入れることができ、修士論文の作成にも大いに役立った。
短期在外研究から、もう一つ思いかげない体験を得た。それは、ちょうど冬季コース期間中には、イスラエルのパレスチナに対するジェノサイドにあたるとして南アフリカが軍事作戦の停止などを求めた訴訟は、隣の建物にある国際司法裁判所で同時に進行していた。裁判所まで来た支持者の正義を求める強い気持ちを共感しながら、人権の最大限の保護を達成するために異なる国のより良い相互作用を確保することができる点で、ICJの人権規範の増進への貢献を実感できた。お互いに人権を守り、守られる社会を共に作る時代になるために、国際社会の中で主権国家にさらに連帯・協力を求める一方、国家以外の第三者の立場に立つ国際機関の役割及び国際法の大切さを改めて認識できた。
林偶之(D3)・中国
概要
「公判中心主義」の改革をどのように推進するかという問題について、中国の学界と実務界の見解は鋭く分かれている。裁判所に代表される実務界は、改革の範囲を公判手続の改革に限定しようとするのに対し、学界では公判前手続、とりわけ捜査手続の改革も不可欠だという見解が主流である。これまでの議論を踏まえて、筆者の博士論文では、第一に公判前手続の改革の必要性の有無、第二に公判手続のみを改革して公判中心主義を実現する方法、という二つの大きな論点について論じる予定である。
論点1については、中国の主流学説は、1990年代に提唱された「刑事訴訟の縦構造論」を議論の前提とするものである。筆者は、日本の刑訴理論を体系的に研究した結果、中国の「刑事訴訟の縦構造論」には議論が不十分な点が多く、これを中国の刑事司法改革を導く基礎理論として用いることには問題があるのではないかと考えている。しかし、筆者が現在構想する議論は、中国の主流学説とは異なるものであり、中国学界に受け入れられるかどうかを見極める必要がある。
論点2については、筆者が3年前に行った実証的な研究によれば、中国における公判手続の改革の成果は非常に限定的であった。これに対して、日本では裁判員制度を契機とした公判手続改革が顕著な成果を上げている。
そこで、今回の訪中研究は、以下の2点を目標としている:
①中国における「刑事訴訟の縦構造論」の問題点について、中国の研究者と意見交換を行う。上海交通大学のS教授は、中国の有力研究者であり、また中国で最も早く「公判中心主義」の実現を主張した研究者である。S教授は、筆者の問題意識に興味を持ち、同大学の教授を招いて筆者の報告を共に聞き、意見交換を行うことに同意してくれた。
②資料、特に実務運用に関する資料を収集する。まず、中国学界の最新研究成果を確認するために、現地の大学等で資料収集を行う。加えて、中国ではほとんどの司法統計資料が公開されていないため、中国の実務運用の現状を把握するために、裁判所に赴き、資料収集、裁判傍聴その他の実地調査及び裁判官等の実務家との意見交換を行う。今回は、異なる地区の実務運用の比較研究を行うため、2つの地域の裁判所に赴き、それぞれ1週間ほど滞在して調査を行う予定である。1つは、試験的改革の模範機関となっている四川省成都市の地方裁判所と中級裁判所、もう1つは、重慶市又は広東省広州市の裁判所である。S教授からは、関係する裁判所との連絡・調整に協力することの同意を得ている。
成果
1 上海交通大学と四川大学(成都市所在)の教授4人と、公判中心主義の実現と公判前手続の改革との関係について意見交換を行った。上海交通大学の2人教授は、博士論文は日本の公判中心改革が中国における刑事裁判のあり方に与えた示唆について論じるにとどめ、日本の公判前整理手続と証拠調べ手続の経験に焦点を当て、訴訟構造改革の問題にまで拡大すべきではないと提案した。その最大の理由は、英米の刑事手続が刑事手続の理想モデルである審判中心の訴訟構造を完全に体現しているのに対し、日本の近年の改革は公判前手続に触れておらず、捜査に対する司法の統制や抑制も弱く、英米に比べて差があると2人の教授は考えているからだ。そして、訴訟構造改革に関する検討は、英米やドイツなどの国の刑事手続を網羅的に理解できるようになった将来に委ねてもいいのではないか、という意見もある。四川大学のL教授とW毅教授は、中国における「審判中心主義」とは、実体形成過程における審判の中心的地位を確保することであると理解すべきであるという点で私と同意見である。この点に関して、L教授は、中国における刑事訴訟全体の性格に関する分析が不十分であり、この点で日本の学説を紹介することは重要であるという私の理解に同意している。同時に、L教授は、捜査に対する司法的抑制や統制を強化することが非常に必要であり、この問題が「審判中心主義」という概念の下で議論されなくなったとしても、より適切な概念を再発見して、関連する議論を導くべきだと提案した。 W教授は、中国では調書裁判の慣性が強いため、捜査と裁判のつながりを短期間で断ち切ることはできず、仮に実体形成過程における審判の中心的地位の確保という点で審判中心主義を理解しても、その実現は難しいのではないかと心配している。
2 成都と広州の各裁判所を訪れ、廷審実質化改革の現状を考察した。裁判傍聴や多くの裁判官との意見交換を通じて、廷審実質化改革に関する中国の現状をより明確に理解することができた。現時点では、「廷審の実質化」改革の成果は限定的で、試行改革では相当数の問題が生じ、改革も行き詰まっている。具体的には、(1)廷前会議制度について、①廷前会議に付された事件の割合は極めて低い、②行われた廷前会議において、a争点及び証拠の整理方法が混乱している、b廷前会議の効力、すなわち裁判所は廷前会議で特定の事項を処分できるかどうかがが明確でない、(2)証拠調べ手続について、③証人の出頭率は依然として低い、④書証に関する検察側の立証は比較的簡略で片面的であり、(3)非法証拠排除規則について、⑤「非法証拠」に関する審査・排除手続の発動率や排除率が全体的に低い、⑥証拠収集の合法性についての証明方法や「非法証拠」の排除基準が明確でない、などの問題が顕在している。これらの問題をどのように解決するかが、博士論文における分析の焦点となる予定である。
王佳敏(D3)・中国
概要
研究課題
「独立した請求のない第三者の訴訟参加とその再構築」を題名に博士論文を書いている。そこには、中国の法院での実務的な運用を調べないと明確にできないところが二つある。一つは、実務的には、同一人が独立した請求のない第三者たる地位および被告たる地位を付与される可能性があるか、そして独立した請求のない第三者が自己に対する請求の定立によって「被告」たる地位を兼ねる手続はどのように行われるか、である。もう一つは、独立した請求のない第三者がいる訴訟において弁論主義がどの程度で適用されるのか、ということである。したがって、「中国の独立した請求のない第三者に関する実務的運用」を中心的な課題に、中国の研究者および裁判官と交流を行う予定である。
活動内容
12月6日から12月7日 大阪経由中国へ帰国
12月8日から12月9日 中国政法大学の民事訴訟法研究所 研究会
12月10日から13日 中国政法大学の証拠科学研究所 Fada Institute of Forensic Medicine & Science(中国政法大学科学鑑定研究所)の見学、研究会等
12月13日から12日16日 北京市海淀区人民法院 見学、審理の傍聴、裁判官との交流会等
12月17日 清華大学を訪問
12月18日 大阪を経て京都へ帰る
成果
12月8日~12月12日
中国政法大学民事訴訟法研究所および中国政法大学科学鑑定研究所を見学した。また、中国政法大学の民訴法学者が主催する研究会に参加した。各研究会のテーマ、参加者およびその内容の要約を次のようにまとめる。
12月8日
テーマ:判決の証明効及びその制限
場所:中国政法大学科研ビールB104
参加者:紀格非教授、史飚教授、最高人民法院の判事1名、中国政法大学の大学院生等
内容の要約:
(1)判決効の規定上の根拠。判決効を法的に認めるのは最初に1991年民訴法司法解釈の75条5項に見られ、現行民訴法司法解釈93条1項5号に置かれている。同条によれば、人民法院による確定した裁判において認定された事実につき証明することを要しない、ただし当事者が覆すに足る証拠を有するときには、この限りでない旨が定められる。注意すべきなのは、民訴法司法解釈93条は証明の領域の規定であり、それと同じ内容を規定するのは、2001年に制定され、2019年に改正された証拠規定の10条である。証拠規定10条1項6号によれば、人民法院による確定した裁判において認定された主要事実につき証明することを要しない、ただし当事者が覆すに足る証拠を有するときには、この限りでないと規定されている。
(2)証明効の主観的範囲、客観的範囲、および効果という三つの観点からのディスカッション。証明効は対世的効力であるため、拘束されるものは現実に訴訟に関与したかどうかとかかわりなく、主観的範囲には制限がないのである。客観的範囲については一定の制限がある。実務上、欠席判決または判決における自白された事実には証明効が及ばないのである。それ以外の事実について、判決理由中の事実認定であれば、証明効が生じる余地がある。判決の証明効の効果については、学説と実務と対立するところである。同一の事実につき、後訴法院の認定は確定判決中のそれと異なってもよいとするのが学説上異論のないところである。これに対して、実務では、同一の事実につき、同一の判決でなくとも、唯一の認定しか許されない立場が採られている。
12月9日
テーマ:訴訟物に関連性のある共同訴訟の位置付け
場所:中国政法大学科研ビール504
参加者:紀格非教授、史飚教授、肖建華教授、北京市第二中級人民法院の判事2名、大学院生等
内容の要約:
中国では、併合される二つの請求に関連性がある共同訴訟は理論的には訴訟物に関連性のある共同訴訟と呼ばれている。この5年、訴訟物に関連性のある共同訴訟の位置付けはかなり流行っている民訴法のテーマである。中国では、通常共同訴訟の範囲がかなり限定的であるため、関連性のある共同訴訟は通常共同訴訟として捉えるのが難しい。しかも、実務・理論においては、その場合を必要的共同訴訟と解するのが通説である。その実務的な運用の特徴としては、訴訟共同の必要がないこと、共同訴訟となれば共通の争点について統一的な判断をしなければならないことが挙げられる。
12月10日
活動:見学
場所:Fada Institute of Forensic Medicine & Science(中国政法大学科学鑑定研究所)
担当者:史明洲副教授
中国政法大学証拠法科学研究所(IELFS)は2006年5月20日に設立された。中国政法大学の科学技術パーク内に位置する同研究所は、1500平方メートルの実験室(サンプル室を含む)と400平方メートルの応接室を含む6000平方メートルのオフィスと実験スペースを有している。研究所のチームは総勢77名で、53名のライセンス鑑定士が在籍しており、その40%がその分野の上級称号を持ち、3分の2が海外交流経験者である。年間11000件以上の鑑定案件が中国、中国の香港、中国の澳門および中国の台湾から寄せられ、報告されている。
12月11日
テーマ:多数当事者訴訟における弁論主義の運用
場所:中国政法大学科学鑑定研究所会議室1
参加者:史明洲副教授、劉子赫博士研究員、北京市第三中級人民法院の判事1名、北京市第三中級人民検察院の検察官1名、大学院生3名等
内容の要約:
1980年代、実体的真実主義のもとで、民訴法においても職権探知主義が採用された時期があった。それと同時に、当事者には訴訟の主体たる地位を認め、裁判の資料を提出する機会を十分に保障しなければならないとする基本的な立場がとられている(民訴法12条)。2000年前後、民訴法12条が法院を拘束しないものであると指摘し、中国民訴法における弁論主義(中国語:弁論原則)を非拘束弁論主義と呼ぶ批判が相次いでいる。これを受けて、2001年「証拠規定」の施行は職権探知主義から弁論主義への転向の端緒を開いたとされている。2000年から、民訴法学者は弁論主義の理念の拡がりを押し進めるために努力してきている。その努力が実った成果としては、前掲のような弁論主義の発露となる条文が数多く設けられたことがある。もっとも、民訴法理論・実務において、実体的真実発見と職権探知主義との理念が持つ影響力は強いから、弁論主義が貫徹されないところが多い。ことに請求のない第三者がいる場合を含める多数当事者訴訟では、法院は主要事実の主張者を問わず事実認定をするとか、自白の成立に慎重な態度をとることがよく見られる。
12月12日
テーマ:私鑑定
場所:中国政法大学科学鑑定研究所
参加者:張君博副教授、安理法律事務所呉艶艶弁護士、大学院生等
内容の要約:
中国民訴法には私鑑定に関する規定がある。その私鑑定には二つの態様がある。一つは、後述の民訴法証拠規則41条に定められれる私的鑑定書である。今一つは、民訴法82条および民訴法司法解釈122条でいう専門家の意見陳述である。前者は鑑定の一種類と解されるが、その客観性や中立性がつねに疑われ信用度が低いものである。実務的には、信用度の比較的に高い私鑑定としては、評価されている調査会社による作成される火災損害額調査表が考えられる。後者は当事者の陳述とみなされており、当事者の補助者の性格を有するといえる。
民訴法79条は当事者による鑑定の申出、法院の職権による鑑定の依頼と鑑定人の指定を定めている。
鑑定人の指定とはいえ、実務的には、鑑定の中立性を保つために抽選という形で鑑定人の選択が行われている。一般的には、当事者の鑑定の申出が各区人民法院によって認められる必要がある。申出が認められた後、区人民法院の裁判官の立会で当事者は中級人民法院(組織としては、区、中級、高級、最高人民法院がある)へ鑑定人のリストから抽選を行う。鑑定人のリストは専門分野ごとに作成され、中級人民法院によって保存されている。また、このリストには全国の資格のある鑑定人が含まれる。したがって、時々、北京市の人民法院に係属する事件の当事者が上海市の鑑定人を抽出することがある。実務上、よく見られる鑑定書としては、警察署によって作成される交通事故の過失割合認定書がある。そこでの過失割合に係る認定が非常に信用度が高く、人民法院によって認められる可能性が高いものである。
12月12日~12月16日
北京市海淀区人民法院民事事件第3法廷を見学した。また、審理を傍聴し、裁判官に裁判資料の整理を手伝った。裁判資料を整理する中、裁判官たちと実務的な慣行や実務的な姿勢等をいろいろ交流した。請求のない第三者がいる訴訟を含む多数当事者訴訟が審理される場合、中国の実務的な傾向としては、以下の4点が挙げられる。
第一に、裁判官は積極的な役割を果たしている。例えば、当事者の一方がある事実につき主張・立証した後、裁判官はその者によって主張される事実や目の前に同事実がどの程度立証されているかを相手方当事者に要約、説明し、相手方当事者の主張・立証を促す場合がある。
第二に、原告は同一の法律関係基づき自己に対して責任を負う可能性がある複数の相手方すべてを被告として訴える傾向がある。例えば、債権者は主債務者と保証人を共同被告として訴えを提起するのが一般的である。このに対し、保証人のみを訴える事例が稀である。
第三に、裁判官は中国の民訴法によって当事者を追加する権限を有する。しかも、固有必要的共同訴訟の場合、脱漏する当事者を追加することを自己の責任であると感じる裁判官が多い。
第四に、中国の裁判官は正義感が強い。例えば、挙証能力を欠く社会的弱者に偏る取扱いがよく見られる。
12月17日18時~20時
清華大学に訪問した。王亜新教授、陳杭平教授、清華大学の院生一人に博士論文の要約を報告し、貴重な意見をいろいろもらった。
KIM MINJUN(D1)・イギリス
概要
本計画は、イギリスの国立公文書館(The National Archives)にて1960-70年代における日印関係に関する史料を集めることである。更に、インドの安全保障の中で重要な分野である印ソ関係、印中関係、印越関係(ベトナム戦争)、核関係などに関する文書も収集することである。そして、TNAにて申請者の研究における分析に必要となる日中関係、日本と東南アジア諸国との関係、核関係に関連する文書も収集する。そして、副次的にイギリスの書店において研究に必要な書籍を購入する。
これらの史料を集める目的は、申請者の研究に使うためである。申請者は、1964-1974年の日印関係を研究しており、研究のために日本側、インド側の史料を集めて必要な研究に使っている。しかし、国際政治史の特徴上、史料批判・検証のためになるべく様々な観点が入っている史料を読み解く必要性があるし、特にイギリスはインドと英連邦という関連性から、インドと関係のある公文書を沢山持っている。
例えば、インド外交史を研究する先行研究者の中(例えば、Madan,Tanvi. Singh, Zorawar等)ではインドの史料だけではなく、アメリカとイギリス史料も参考にしている研究者もいる。そのため、申請者は、実証性を更に引き上げるために、国際政治的に重要な論点に関わる史料収集によって申請者の研究に国際政治学的な解釈を更に与えるためにイギリスのロンドンに史料調査に行こうと思ったのである。
成果
申請者は1月30日2月3日、2月6日から2月10日までイギリスの国立公文書館に訪問して必要な史料を収集することができた。更に申請者は、追加的に研究に使うために本体想定していなかった印英関係、印米関係文書も集めることができたのである。これらは日印関係文書とインドの安保懸案と関係のある史料であり、日中関係、日本と東南アジア諸国との関係も参考・研究分析に使うための史料として収集することができたわけである。
今回のイギリスの国立公文書館における史料調査のおかげで本人の研究に必要な史料を収集することができ、本人の研究における実証性を更に引き上げることができ、研究の進行に役立った。即ち、当初申請者が想定していた史料をほとんど収集することに成功し、更に間接的に役立つ史料も収集することができた。