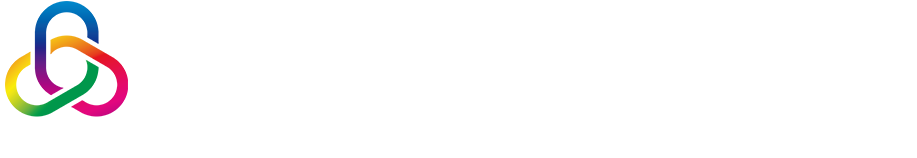教育活動
関連科目の概要紹介
【近藤正基】
- 政治過程論(法学部)
福祉国家を比較するための理論、スウェーデン、アメリカ、ドイツ、日本といった主要国の事例、今後の福祉国家の展望について講義しています。 - 演習(法学部)
福祉国家が直面する問題群と、各国の政策的対応について学びを深めます。 - 政策決定過程論(公共政策大学院)
グローバル化とポスト工業化が先進工業国の政治に及ぼす影響について検討します。
【稲森公嘉】
- 社会保障法(法学部)
わが国の社会保障の法と制度について、その正確な現状認識と基礎的な理解を得ることを目的として、その概要及び主要な法的論点について講じます。 - 社会保障と法(全学共通科目)
私たちの日々の暮らしを支えている社会保障制度の内容を概観します。 - 社会保障法(法科大学院)
社会保障法を構成する各制度(労災補償を除く。)の基本的枠組みについて、給付に関する受給者の権利義務を中心に、財政的側面やサービス提供体制等を含めて概説するとともに、関連する法解釈上及び政策上の論点を検討します。(公共政策大学院の「社会保障法政策」と共通)。
【木村敦子】
- 演習(法学部)
親族法や相続法について、先行研究に関する文献を講読するなどして基本的な知識の修得に努めるほか、生殖補助医療や同性カップルの法的取扱いなど先進的な問題を取り上げ、民法や法哲学等の観点も踏まえながら、今後の家族のあり方や家族法制について考察しています。
【嶋田博子】
- 公務員制度(公共政策大学院)
国家公務員の人事管理につき、企業や他の主要国との異同と理由を説明するとともに、政官関係の変遷が公務員・国民にどう影響しているかを検討します。 - 行政官の役割規範(公共政策大学院)
言語哲学の視点を踏まえつつ、中立性・専門性・全体の奉仕者といった規範の解釈をめぐる言説の変遷と、国民への倫理的責任を考察します。 - 現代政策と公共哲学(公共政策大学院)
ケーススタディ方式で、公権力にまつわる近現代の思想家の代表的著作を下敷きにしつつ、実際の政策における価値の衝突をとらえ直します。 - 人事・労働政策分析(公共政策大学院)
ケーススタディ方式で、働き方改革はじめわが国の労働政策に関する具体的提案及び多様なステークホルダーとの調整を模擬体験させます。
【島田裕子】
- 労働法(法学部)
個々の労働者と使用者との契約関係(雇用関係)について最低基準を設定し、公平な利益バランスを実現しようとするための法律や、労働組合と使用者との集団的な関係を規律し、公正な労働条件を集団的に決定するための法律について扱っています。
【島田幸典】
- 比較政治学(法学部)
イギリス・ドイツを中心に、ヨーロッパ諸国における民主的国制の形成と発展、多様性やその背景、課題などについて比較史観点から考察します。 - 演習(法学部)
欧州諸国の政治について、比較論的・歴史的見地から検討した文献に基づき検討し、その知見が現代民主政治にたいしていかなる示唆をもつか考察します。 - ヨーロッパ政治(公共政策大学院)
ヨーロッパにおける国家の発展と多様性をもたらしたものをめぐって理論的・歴史的見地から検討するとともに、今日各国が直面する政治課題について多角的に考察します。
【田中晶国】
- 租税法(法学部)
租税法に関する基礎理論と租税の実態について理解することで、現代社会に適した租税法のあり方への重層的な考察を可能にすることを目標として、所得税法・法人税法・消費税法を中心に講義しています。 - 演習(法学部)
租税法にまつわる諸問題について演習形式の授業を行っています。所得種類、所得控除や所得の帰属など、租税法において、家族と働き方に複雑な影響を与える諸規定が存在しています。演習では、現代の家族関係に適した税制のあり方についても議論を行っています。