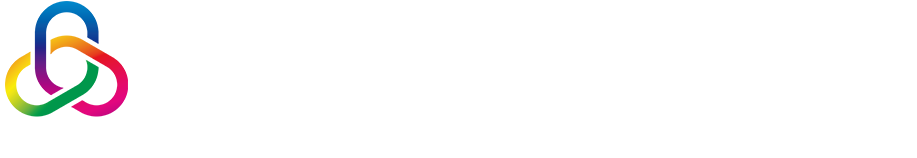研究活動
研究プロジェクト
少子化・高齢化問題を論じるためには、学問分野横断的な視点が求められます。社会保障政策のみならず、家族政策、財政政策、移民政策と結びつけて、多角的に分析する必要があります。また、対策の決定過程を明らかにするためには、政治学・行政学的アプローチが欠かせません。本ユニットでは、比較政治学、行政学、社会保障法、家族法、労働法の研究者が、国内外の専門家と協働しつつ、以下の4つの研究を進めます。
1.先進工業国における少子化・高齢化対策の展開と、これに伴う福祉国家変容を分析します。政策決定過程における政党や団体の役割に注目しつつ、様々な取り組みが見られるヨーロッパ諸国や、急速な高齢化に直面している東アジアの国々と比較することで、日本の政策的・政治的特徴を明らかにすることを目指します。
2.政治的指示の実現に向けた官僚制への要求が強まる一方、少子高齢化という課題は、利用可能な資源、個人の基本的生への関与という両面から応答限界があります。行政はどこまでの対応が可能/適切か、どうすれば国民の納得が得られるのかに関し、日本の官庁現場が直面する課題を先進諸国のそれと比較することで、今後の政策選択肢を提示することを目指します。
3.急速な少子化・高齢化の進行は、年金・医療・介護をはじめ、社会保障制度や労働法制、税制にも大きな影響を及ぼしています。そのような人口見通しの下で、今後も持続可能な社会保障制度や労働政策、税制策の在り方を、法学を中心とした学際的観点から検討し、具体的な政策選択肢の提示を目指します。
4.民法が定める婚姻や親子に関する諸制度の内容・運用の検討を踏まえ、その背後にある家族やライフスタイルのあり方を分析することで、少子化・高齢化問題の要因を探り、具体的な政策提言に取り組みます。
研究会記録
2024年度
・2024年3月、京都大学法学研究科、同法政策共同研究センター少子高齢化ユニット共催、Wolfgang Drechsler教授(Tallinn University of Technology, Harvard University Davis Center)(公共哲学)を招聘した公開セミナー。
①Administrative Capacity and Aging Society: Challenges and Continuity in the Age of Kiddultism(3月11日)
高齢者増加がもたらす課題は、幼さをもてはやす現代文化の見直しを迫るのか、それとも伝統との連続性を持つのか。国家はこの課題に行政的に、あるいは行政組織としてどう対応すべきか。G.ガダマーの後継者であるドレクスラー教授はこうした問題について、歴史、哲学、文化の視点から分析し、政治学・行政学・法学の観点から活発な議論が行われた。
②From the New Public Management to the Neo-Weberian State(3月16日)
多様なウェーバー論と国家の主導力を強調する近年のNWS(新型ウェーベリアン国家)との結びつきを論じた上で、なぜ市場原理を適用するNPMの動きが生じ、その後力を失ったのか、ウェーバー型国家に対するウェーバー自身の批判、執行における衡平・包摂確保への意義、「目的合理的行政」の今日的意味を考えるドレクスラー教授の報告後、価値が衝突する行政課題解決に向けたNWSの可能性について、ユニットメンバーや行政学研究者との活発な議論が行われた。
・2024年9月9日から11日 京都大学法学研究科、同法政策共同研究センター少子高齢化ユニット、ウィーン大学法学部共催「少子化問題へのアプローチ――学際的・国際的観点から」
2024年9月9日から11日まで、ウィーン大学法学部の研究者を招へいし、「少子化問題へのアプローチ――学際的・国際的観点から」というテーマで、国際シンポジウムを実施した。日本側からは、木村敦子(本ユニットメンバー)“Die Ehe aus dem Blickwinkel der Problematik des Geburtenrückgangs”、栗村亜寿香(京都大学教育学研究科 研究員)“Background to the Declining Birthrate and Characteristics of Unmarried People in Japan”、大竹文雄(京都大学大学院経済研究所 特定教授)“Addressing the increasing unmarried rate from a perspective of behavioral economics”、近藤正基(本ユニットメンバー)(本ユニットメンバー)“Kinderbetreuungspolitik in Deutschland und Japan”という研究報告が行われた。ウィーン大学からは、Mag. Helene SCHNABL (Institut für Arbeits- und Sozialrecht)“Arbeits- und Sozialrechtliche Rahmenbedingungen der Realisierung des Kinderwunsches”、Dr. Sonja DÖRFLER-BOLT (Institut für Familienforschung)“Familienleistungen in Europa”、Mag. Lorenz WURM (Institut für Familienforschung)“Familienleistungen und Geburtenentwicklung”、Dr. Peter DENK (Institut für Finanzrecht)“Familienlastenausgleich” という研究報告が行われた。3日間にわたるシンポジウムでは、対面・オンライン参加者を含めてのべ約100名の国内外の研究者や学生が参加した。各研究報告を通じて、少子高齢化問題あるいはその背景にある社会状況について、日本及びオーストリアの法学・政治学・経済学・社会学等の知見が共有され、具体的な労働政策・社会保障政策のほか、働き方や家族生活に対する意識の違いとそれを支える社会インフラ・法制度のあり方について、活発な議論が行われた。
・2025年3月28日(法政策共同センター法文化共同研究セクションとの共催): Anne Röthel氏講演会“Familienrechte unter den Bedingungen der Moderne”
ドイツのマックス・プランク外国私法・国際私法研究所所長のAnne Röthel氏を招へいし、“Familienrechte unter den Bedingungen der Moderne(現代の状況下での家族法)”というテーマでのご講演をしていただき、それに関する意見交換を行った。国内外総勢20名程度の研究者が集まり、近時の欧州における家族法制度に関する知見を共有するとともに、家族法制、家族法政策、あるいはそれらの背景にある家族のあり方や家族観について、比較法的、学際的観点から活発な議論が行われた。
主たる研究業績
2024年度
近藤正基 教授
- Das wohlfahrtsstaatliche Reformkonzept der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft von 1992 bis 1994, Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 1-11, 2025.
- Wohlfahrtsstaat und Parteipolitik in Japan: Soziale Sicherung unter Druck, Friedrich-Ebert-Stiftung (“Labor and Social Justice” Series), S. 1-24, 2025.
- Kinderbetreuungspolitik in Deutschland und Japan: Eine vergleichende Analyse der Reformprozesse in den Amtszeiten Angela Merkels und Shinzo Abes, INDES. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 03-04/2024, S. 88-99, 2024.
- Steuerpolitik in Deutschland und Japan: Vergleichende Studie der Politik der Mehrwertsteuerreformen, Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 1-16, 2024.
稲森公嘉 教授
- 「子ども・子育て支援金と医療保険料」週刊社会保障3293号44-49頁
- 「育休取得中の保育の利用継続不可決定・利用解除処分の執行停止」岩村正彦・水島郁子・笠木映里編『社会保障判例百選〔第6版〕』(有斐閣、2025年)200-201頁
木村敦子 教授
<著書・共著>
- 大村敦志・窪田充見編『解説 民法 (家族法) 改正のポイントI 2018〜2022年民法改正編』(有斐閣、2024年)(分担:生殖補助医療に関する特則(187-202頁))
<論文、判例評釈、討論等>
- 「私的自治論からみた親権の再構成に関する覚書――財産管理権及び法定代理権の位置づけを中心に――」法学論叢196巻4=5=6号392-434頁
- 「第三者提供精子を用いた場合における法的親子関係について──同意の意義に関する検討を中心に」大村敦志ほか編『家族法学の過去・現在・未来』(有斐閣、2025年)425-454頁
- 「 死亡保険金受取人を「相続人」と指定した場合の死亡保険金と相続財産 」洲崎博史=後藤元編「保険法判例百選[第2版]」 (別冊ジュリスト271号)150-151頁
- 「民法学における法解釈方法論の歩み:吉田邦彦『債権侵害論再考』」、「家族法学と法解釈方法論・法学方法論:水野紀子「中川理論——―身分法学の体系と身分行為理論に関する一考察」」𠮷永一行編『民法理論の進化と革新 : 令和に読む平成民法学の歩み出し』(日本評論社、2025年)355-367頁、422-435頁
- 「判例詳解 法的親子関係の成立における性別の意義[最高裁令和6.6.21第二小法廷判決]」ジュリスト1605号112-119頁
- 「シンポジウム「高齢者を委託者とする家族間信託の現状と課題」 設定上の課題」信託法研究48号59-83頁
- 「遺産分割前の財産の処分に関する検討」潮見佳男先生追悼論文集(家族法)刊行委員会編『家族法学の現在と未来』(信山社出版、2024年)541-558頁
- 〔共著〕「家族法判例総評:2024年度〔第1期〕」戸籍時報855号11-22頁 (※羽生香織との共著)
<講演、口頭発表等>
- シンポジウム「高齢者を委託者とする家族間信託の現状と課題 設定上の課題」、相48回信託法学会、2024年6月9日
- Die Ehe aus dem Blickwinkel der Problematik des Geburtenrückgangs, 2024年度ウィーン大学・京都大学共同セミナー(Wien-Kyoto Seminar 2024), 2024年9月9日
- Gender Diversity and the Law 、台湾大学京都大学学術交流研究会 「未来社会と法律」に関する日台学術対話、 2025年3月10日
嶋田博子 教授
<著書・共著>
- Koichiro Agata, Hiroaki Inatsugu, Hideaki Shiroyama (eds.), “Public Administration in Japan” (Palgrave Macmillan, 2024) (分担:第11章The Civil Service and Public Employment(pp.133-202:小西敦との共著))
<論文>
- 〔共著〕Balancing Continuity and Change: Japan’s Pursuit of a ‘Small and Strong’ State Within the Neo-Weberian State Framework, Journal of Policy Studies 39(3) 1-11. (Koichiro Agata, Dimitri Vanoverbekeとの共著)
- 「NWS(Neo-Weberian State)はNPMを上書きするか――各国適用可能性をめぐる議論の動向――」季刊行政管理研究187号27-41頁
<講演、口頭発表>
- 「官僚制はデモクラシーを支えられるか -ポピュリズムの時代におけるプロフェッショナリズム-」人事院公務員研修所 行政フォーラム, 2025年1月21日
島田幸典 教授
<著書・共著>
- 日本比較政治学会編『比較政治学事典』(丸善出版、2025年) (担当項目「国家と
は何か」)
田中晶国 教授
<論文>
- 「賃上げ税制」ジュリスト1600号27-32頁
<講演、口頭発表>
- 「第53回租税法学会 コメント」, 租税法学会, 2024年10月
- 「租税法における法的思考と要件事実」, 全国女性税理士連盟, 2024年6月